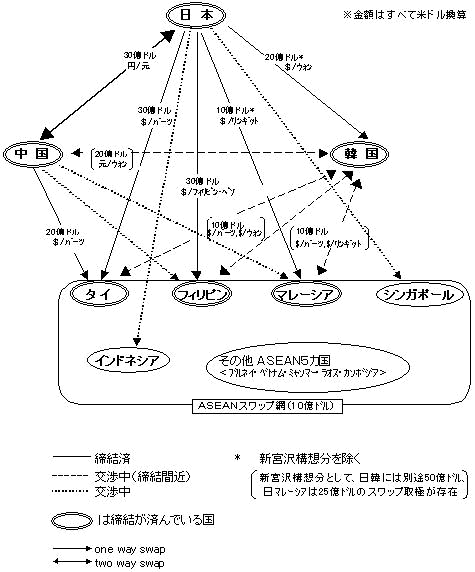
東アジアの成長と地域システム変容
2005/4/5 日本経済新聞社8F
主催:日本経済研究センター 日本経済新聞社
講演
余永定 Yu Yongding 中国社会科学院世界経済・政治研究所所長
1969年中国科学院中国科学技術大学卒業。1979年中国社会科学院世界経済研究所入所、86年中国社会科学院研究生院で経済学修士。94年オックスフォード大学で経済学博士号取得。中国世界経済学会会長、中国人民銀行貨幣政策委員会委員を兼務。編著、共同編著は10冊以上、マクロ経済、世界経済などについて多数の学術誌に論文を多数掲載。
マーカス・ノーランド Marcus Noland 国際経済研究所(llE)シニア・フェロー
1981年スワスモア大学卒業。ジョンズ・ホプキンス大学にて修士・博士号取得し、1985年国際経済研究所入所。1988年〜1989年埼玉大学客員教授。他に、南カリフォルニア大学、東京大学、ガーナ大学などでも客員教授を務める。米国の貿易政策、アジア経済問題を専門とするが、最近は朝鮮統一問題なども研究している。
パネルディスカッション
余永定
マーカス・ノーランド
モハメド・サドリ Mohammad Sadli
国立インドネシア大学名誉教授
米カリフォルニア大学(バークレー校)、米マサチューセッツ工科大学卒。国立インドネシア大学で博士号取得。1971−73年人材開発相、73−78年鉱物資源・石油相。スハルト政権時代は大統領の経済アドバイザリーグループの一員。インドネシア投資委員会の初代委員長も務めた。政界引退後は同国商工会議所書記長や同商工会議所系シンクタンクの所長などを歴任。
氏家純一 野村ホールディングス会長
1945年生まれ。69年東京大学経済学部卒業。72年米国イリノイ大学大学院修士課程修了、75年シカゴ大学で経済学博士号取得。75年野村護券株式会社(現、野村ホールディングス)入社。ノムラ・スイス・リミテッド社長、国際企画室長、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル社長などを経て、90年取締役に就任、95年常務取締役、97年取締役社長、2003年4月より取締役会長、6月から兼執行役。
小島明(兼モデレーター) 日本経済研究センター会長
2002年 6月 日本銀行
東アジアの通貨安定に向けた通貨スワップ網の構築
─
東アジア地域のソフトな支援の枠組み作り ─
http://www.boj.or.jp/wakaru/intl/weasia.htm
本稿は日本銀行国際局企画役 曽我野秀彦が広報誌『にちぎんクオータリー2002年夏季号( 6月25日発刊)』に執筆したものです。
さる 3月28日、日本銀行は中国の中央銀行にあたる中国人民銀行との間で、円対人民元のスワップ取極<とりきめ>を締結しました。これは、相手国から要請があった場合、一定の要件が満たされれば、30億ドル相当の円または人民元を互いに融通しあうことを認めたものです。円を対価とするスワップには、過去、ドルやユーロ(注1)を使ったものはありましたが、アジアの通貨では初めてのケースになります。
(注1)ユーロの発足前は、欧州の主要通貨とスワップ取極を締結していました。
この取極の締結に至るまでには、紆余曲折がありました。東アジア地域における金融面の相互支援体制については1997年のアジア通貨危機前から検討されていました。日本が中心となって、国際通貨基金(IMF)のアジア版ともいうべきAMF構想を打ち出してみたわけですが、IMFとの関係に懸念を示した米国や、日本の顔が出過ぎることに対する反発がアジア諸国からもあり、国際金融界からは賛同を得られなかったのが実情です。そこで、その後よりソフトな路線への転換が模索されました。
2000年 5月、東南アジア諸国連合(ASEAN)10カ国に日本、中国、韓国の 3カ国を含めた13カ国(以下、「ASEAN+3」)の財務大臣クラスの会合で、「 2カ国間での金融取極をそれぞれが相互に結ぶことを通じて支援体制を構築すること」が合意されました(会議が開催されたタイの地名を取って「チェンマイ・イニシャティブ」と呼ばれています)。この枠組みは、集団的な金融支援体制として、為替投機等の動きを牽制するとともに、為替・金融市場の安定を図ることを目的としています。また、東アジア地域の域内協力となっていますが、IMF支援を含む既存の国際的な資金支援制度を補完するものと位置付けられています。取極は基本的な内容の統一を図りつつも、その実際の発動にあたっては、参加各国が決定権を持っており、必要な国に対する資金の融通を決定することになります。
もともとASEAN諸国内には、総枠 2億ドルのスワップ取極が存在していましたが、この規模を10億ドルに拡大するとともに、日本がリードする形でASEAN+3メンバー内における 2国間スワップを広げることになりました。昨年までに日本は韓国、マレーシア、タイ、フィリピンと取極を締結し、今回これに中国が加わりました。さらに、現在シンガポールやインドネシアとも交渉を行っています。また、中国は日本以外にタイと既に締結し、現在韓国、マレーシア、フィリピンと交渉中です。韓国も、日本と締結後、中国、タイ、フィリピン、マレーシアを相手に交渉を進めています。こうした形で、アジア域内でのスワップ・ネットワークの構築が進んでいます(図)。
(図)チェンマイ・イニシャティブに基づく
2国間スワップ取極(2002年 5月現在)
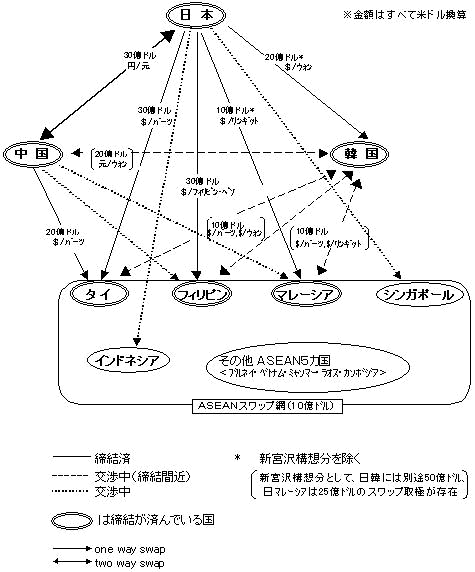
日中スワップの意味するところ
今回の日中スワップ取極締結にあたって特筆すべきことが幾つかあります。
その一つは、東アジア地域の国境を跨った相互支援体制に中国が初めて加わったことです。アジア通貨危機を経験し、おそらく中国も、高度成長を持続するためには国際金融、特に東アジアの金融安定化が不可欠であることを認識したものと思われます。中国は世界貿易機関(WTO)加盟後、自由貿易協定(FTA)をASEAN諸国と結ぶべく交渉を開始するといったように、国際経済社会の中での橋頭堡を築き上げるべく明確な意思を示しています。こうした中国の行動は同時に自国を外部のリスクに晒すことにも繋がるわけです。その際に、地域協力をもってリスクを軽減化させることが得策と考えたとしても不思議ではありません。
第二に、今次取極の内容にも特徴があります。すなわち、日本がこれまで中国以外のアジア諸国と結んだ取極は、日本が「一方的にアジア各国に資金を融通する」ものでした(注2)。これは、外貨流動性危機に陥った国からの要請があれば、わが国は保有する豊富な「米ドル」を現地通貨と交換することを約束するという「危機対応」を主たる目的にしたものでした。
(注2)チェンマイ・イニシャティブに基づく、日本と韓国・マレーシア・タイ・フィリピンと締結した取極は、いずれもドル対現地通貨のスワップで、日本から相手国へ資金融通を行うものです。また、1998年に打ち出された東アジア向けの資金支援スキームである「新宮沢構想」に基づく取極(韓国およびマレーシアと締結)も、日本からアジアの国に向けた一方方向の供与でした。
これに対し、今回日本銀行と中国人民銀行との間で締結された日中間のスワップは、「円と人民元を対象」として、両国間が対等な立場で取極を結び、両国がいずれも資金を融通しあう立場で契約を結んだことが特記すべき点です。
中国の外貨準備は、2001年 3月末で2300億ドルと、今や日本に次ぐ世界第 2位の規模にまで膨らんでいます。このため、このスワップ取極がいわゆる目先の有事対応を念頭に結ばれたものでないことも明らかです。しかし、平時でも為替相場にいかなる圧力がかかるかはわかりません。日本銀行もかつて1964年にIMFの 8条国移行に先立って、円とドルのスワップ取極を米国ニューヨーク連銀との間で締結した経緯があります。中国が今後各方面で自由化を進めていく過程で、金融為替市場の安定策の一つとしてこうしたスワップ取極を用意しておくことは意味のあることです。
また、円と元をスワップの対象にしたという点では、両国間の貿易取引が実際にはドルをベースに結ばれる契約が多い中で違和感を持たれる向きがあるかもしれません。しかしながら、アジア域内の金融安定化を図る上では、域内通貨価値の安定にまずは主眼が置かれるべきでしょう。チェンマイ・イニシャティブの枠組みでは、スワップを締結する当該国通貨間での取極を結びあい、ネットワークを構築することが求められています。
さらに、今回、日中間で結ばれた取極により、アジアにおける円の利用の促進といった効果も期待されるほか、同時に、現在国際交換性に制限のある人民元がこうした取極に使用されることにより、国際通貨としての位置付けを一歩前進させることに繋がっていくかもしれません(注3)。
(注3)中国側が円を引き出した場合には、日本銀行は担保として国際交換性に制限のある人民元を受け取ることになります。こうした点を考慮して、本取極には、日本銀行の資産の健全性を確保するために必要な措置を盛り込んであります。
アジア地域の金融安定化に向けた取り組み
アジア地域の金融安定化に向けた取り組みとしては、こうしたスワップ取極を結ぶだけでは不十分です。例えば、有事の金融支援に先立って、各国の経済状況を互いにモニタリングしあう相互監視体制を確立することが必要です。毎年 5月のASEAN+ 3蔵相会議では、各国の経済情勢について意見交換をする場が設けられていますが、これに加えて、中央銀行からの参加者を含めた代理者レベルでの「政策対話」の場を、この 4月ミャンマーで開催された会議でスタートさせました。さらに今後、より実効性の上がるような仕組みを如何に作っていくか、現在、全参加国の間で議論がなされているところです。例えば、IMFなど既存の国際機関が持っている情報を如何に活用し、各国の経済政策立案にあたって意義のある意見交換ができるようにするには如何なる仕立てにすれば良いか、といった点に関して検討しています。
また、アジア通貨危機の反省を基に、各国の短期資金フローをモニタリングする体制を強化していくことの重要性も共通の認識となっています。外貨準備のデータも、その詳細な内訳を知らずして危機への対応が万全とは言えません。アジア通貨危機の際に、ある国で外貨準備のかなりの部分が実は国内の金融機関が海外支店に保有してあった外貨を計上したものであったことが判明したため、実際に利用可能な外貨は公表額を大幅に下回ることが判明するといった事態もあったほどです。
外貨準備に関する統計は、各国ともに比較的整備が進んでいる方ですが、統計データが十分整備されていない、あるいは開示の範囲が限定的であるために現状を把握することが困難な状況にあることも多いのが実態です。こうした外貨準備をはじめとする各国の統計整備を進める目的から、日本がアジア諸国に対する技術協力を進めることも重要な役割です。例えば、短期資本モニタリングに関するセミナーを日本のイニシャティブでこの 3月に開催し、日本銀行からも講師を派遣したりしています。
スワップ取極は、その交渉を重ねていく過程で、契約の条件に含まれる種々の項目が相手国でどのような状況にあるのかを知る良い機会にもなります。
例えば、取極の中では中央銀行の位置付けや、資本規制を課す主体を明確にしておく必要があります。中国の場合、人民銀行が1995年にできた法律で中央銀行として明確になったものの、(1)政府から独立した存在ではなく、あくまで政府の一組織であること、(2)約15万人の職員を抱える組織のトップである行長は大臣(日本の内閣にあたる最高国家権力の執行機関である国務院のメンバー)であること、(3)金融政策の基本方針は国務院が決定し、外国為替市場の運営・管理、経常・資本取引や外貨準備の管理を実際に行う外貨管理局を人民銀行の外局として取り込んでいることなどが改めて確認されました。また、国際収支データの開示は、現在人民銀行がリード役となってグローバルスタンダードに合わせるように関係当局の調整を行っていることも判明しました。
今後の展望
欧州におけるユーロの導入成功をみて、アジアにおいても単一通貨を夢見る議論も全くないわけではありません。しかし、政治・経済・社会などアジアの多様性を考えれば、欧州の通貨統合アプローチをアジアにそのまま当てはめて考えることは非現実的でしょう。
むしろアジアにおいては、はじめから確固たる制度を設けることなしに、まずは各国が合意できるものから徐々に実現していくという現実的な方法で進んでいくものと思われます。その意味でも、現在ASEAN+3の枠組みで 2国間のスワップ・ネットワークを張りめぐらしていくことはその第一歩であり、これと併走する形で様々な取り組みが進められつつあるのは、まさにアジアらしい国際協調の一つのやり方を示していると言えるかもしれません。
アジアにおいては、ASEAN+3以外にアジア太平洋経済協力会議(APEC)、アジア欧州会合(ASEM)、マニラフレームワークなど1990年以降に発足したフォーラムが数多く存在しますが、中でも中央銀行をメンバーとする東アジア・オセアニア中央銀行役員会議(EMEAP)は組成後10年を経過し、総裁会合、代理会合以外に、決済システム・金融市場・銀行監督のそれぞれに焦点をあてた 3つのワーキング・グループや、本年 2月に新たに発足したITフォーラムなどで活発な議論がなされています。果たして、今後、アジアにおいては如何なる枠組みが存在価値を発揮し、アジア通貨圏がどのような形で構築されていくのか、現時点ではまだ将来を見通せる段階にはありませんが、アジア地域のソフトな相互支援体制が一歩一歩作られつつあることの意義は大きいと考えるところです。
アジア通貨基金(AMF)
http://park5.wakwak.com/~asia/inform/amf.htm (アジアの声)
アメリカのAMFつぶし
タイの通貨バーツ下落による経済混乱の中で、日本は1997年8月のタイ支援国会合を主導した。この会合で、資金拠出をしぶるアメリカとは対照的に、支援体制をリードし、責任を負おうとする日本の意気込みが印象づけられた。このとき、「通貨危機の再発に備え、1000億ドル規模の通貨基金の創設する」という構想が生まれ、いわゆる「アジア通貨基金」(AMF)構想として発表されることになる。
1997年9月中旬から下旬にかけて、香港で開かれた先進7カ国蔵相・中央銀行総裁会議(G7)や、ASEAN蔵相会議など一連の国際金融会議で日本は、AMFを非公式に提案した。
ASEAN各国と韓国はAMFに賛成した。しかし、アメリカはAMFに警戒感を抱いた。「IMF・世界銀行による国際金融秩序を崩す」「独自の支援によって問題国の改革姿勢が甘くなる」というのが理由だ。中国と香港も「出資は難しい」との理由で消極的態度を示した。
当初大蔵省は、アメリカを説得して、なんとかAMFを実現することを目指した。榊原英資財務官(当時)は、1997年11月3日、ワシントンでサマーズ財務副長官(同)と会い、アジアの通貨危機への対応や日本の景気動向などについて意見交換した。
だが、アメリカはAMFを認めなかったのである。11月15日には、IMFのカムドシュ専務理事が、「このような基金が創設された場合、関係国の依存度が極度に高まり、政策面での『自己管理責任』の認識を失わせる逆効果が懸念される」と語り、IMFから独立した地域金融機構の設立は認めないとの姿勢を明確に示した。
この時点で、日本政府はAMF創設を一旦あきらめたのである。
沖縄サミットで提案
ところが、1998年夏、アメリカは態度を変えざるを得なくなった。
1998年8月17日、ついにロシアは通貨ルーブルの事実上の切り下げに追い込まれた。これと前後して中南米、東アジア、南ア、中欧諸国など世界的に株価が急落し、同時に為替レートが一気に不安定化、国際金融市場は混迷の度を深めたからである。
アメリカにとって、中南米の安定は欠かせず、まず中南米に対応しなければならない。とても、アジアにコミットする余力はない。こうして、アメリカは日本のアジアにおける役割を認めざるを得なくなったのではなかろうか。
また、この時点で「IMFの処方箋も万能ではない」との認識が広がりつつあった(→[市場経済万能主義者の敗北]参照)。
こうして、AMFが息を吹き返す環境が整ったのである。
1999年2月9日、アジア危機を教訓に国際経済システム再構築の方策を探る高村正彦外相の私的勉強会「国際経済・金融システム研究会」(座長・行天豊雄国際通貨研究所理事長)の第1回会合が、外務省飯倉公館で開かれた。ここで、AMF構想を実現させることが必要だとして、沖縄サミットで提案することで一致した。
この間、AMF必要論も唱えられていた。韓国の金鍾泌首相は1998年11月28日の小渕恵三首相との会談で、日本を中心として3000億ドル規模のAMFを設立するよう提唱していたのである。
いまや、金首相は、アジアの地域機構のプロモーター的存在になりつつある。彼は、1999年9月には東京で行った日韓協力委員会創立30周年記念講演で、東アジアにおける新たな地域協力システムとして、韓国と日本、中国、ロシアなどによる「東アジア経済協力体」創設を提唱している。ここでも彼は「AMFは論議する価値がある」と述べている。
ここにきて、ASEAN諸国も再びAMF支持を表明するようになっている。1999年9月2日には、マハティール首相がクアラルンプールで開かれたシンポジウム「通貨規制とアジア金融システムのあり方」(毎日新聞社、マレーシア国際戦略研究所、日本貿易振興会主催)で講演し、「AMFはアジア経済回復にとってプラスになると思う」と述べている。
また1999年9月7日に開催された(社)日本マレイシア協会主催のシンポジウムで、タンスリ・アリ・アブル・ハッサン・マレイシア中央銀行総裁は、「AMFがあれば、経済危機が域内に拡大することを防止できた」として、AMFの必要性を強く訴えた。
沖縄サミットは、AMF具現化にとって、大きなステップとなろう。沖縄を控え、2000年2月にバンコクで開催される国連貿易開発会議(UNCTAD)総会でも、AMF構想が話し合われる見通しである。
ワシントン・コンセンサス 田中 宇
円・元・ドル・ユーロの同時代史
第31回〜ワシントン・コンセンサスとは何か
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/rep01/315917 (日経BP BP's
Eye 2004/6/26)
谷口 智彦(編集委員室主任編集委員)
「ワシントン・コンセンサス」とは、いかにも権力的響きを持つ言葉である。ケインズが固執したようにIMFや世銀がニューヨークにあったとし、両機関の指導原理が仮に「ウォールストリート・コンセンサス」と呼ばれていたのだったらどうだったか。市場の力を重視する考えだと思われこそすれ、権力づくの傾向を感じさせることは少なかったに違いない。
ところが幸か不幸かブレトン・ウッズ機関が双方ともワシントンにあったことから、その指導理念が「コンセンサス」と呼ばれてみると、そこに米国の意思や権力の反映を見たくなるのは当然のなりゆきであった。
「ワシントン・コンセンサス」とはもともと、国際経済学者ジョン・ウイリアムソン(John Williamson)が1989年、論文の中で定式化したものだ。80年代を通じ先進国金融機関とIMF・世銀をともに動揺させた途上国累積債務問題との取り組みの中、「最大公約数」(ウイリアムソン)と呼べる10項目の政策を抽出し、列記したものである。
「金利の自由化」や「民営化」、「規制の撤廃」といった項目はどれも、上述した第1の点、すなわち市場の自動調節機能を存分に働かせることを狙った政策だった。「規制撤廃と自由化の『十戒』」 である。
他の項目は次の通り。財政規律の確立、政府支出を、成長促進的な方向、基盤整備的方向に振り向ける税制改革、為替制度自由化、貿易の自由化、直接投資受け入れ、所有権保護制度の確立の7項。
経済に対する政府介入を正当視した「ケインジアン・コンセンサス」に対し、「政府介入はなければないほどよい」と打ち出したもので、レーガン、サッチャーといった米英の指導者が進めた80年代の新保守主義イデオロギーを濃厚に帯びていた。
「規制撤廃と自由化の『十戒』」として語ることのできるワシントンコンセンサスが、ウイリアムソンの論文において命名・定式化されたのは、1989年のことだった。ベルリンの壁倒壊に象徴される東側共産陣営の瓦解と重なったこの年以来、冷戦の終焉という事実は、その後数年の国際環境を規定していく。
米国は、冷戦に勝利した「平和の配当」を求める利己主義的傾向へと転じた。イデオロギー対立にこそ勝利を収めたものの経済力では衰退を続けた事実が、改めて米国人自身の注目を浴びた。冷戦システムにただ乗りし果実をむさぼったとみなされた日本は、「敵」とは言わないまでも、正面のライバルと見られるにいたった。
ここから、円ドル為替レートが1ドル80円割れの史上最高値をつける1995年夏までの5〜6年間は、省みるに日米間の経済摩擦が最も熾烈を極めた時期である。
その反動として日本では、「米国からの独立」を求める心情が強まった時期としてとらえることもできよう。「NOと言える日本」であるべしとした石原慎太郎*2 、日米安保条約の改廃を求めた江藤淳ら保守派の論客は、「脱米入亜」の路線を顕揚(けんよう)した。小沢一郎が政治家として「日本改造計画」を発表、米国追随一辺倒を脱し「普通の国」となる道を唱えたのも、この頃のことである。
日本経済は90年2月初めて本格的株価崩落を見て以来、後に14年続く停滞の入り口へ差し掛かりつつあったけれども、中国は開放経済へ転じたばかりで日本人の視野にまだ入ってきていない。アジアの盟主をもって、自他とも任じていられた時期でもあった。
このように、今振り返るとものの数年に過ぎないけれども、日米の離反、日本の自立志向、アジアにおける競争者の不在といういくつかの傾向が重なり合ったごく短い期間をとらえて、ワシントンコンセンサスへの批判の矢が、東京から放たれたのである。
日本が放った批判の矢
まず紹介すべきは次のような問いかけだろう。
「…輸入自由化が性急になされた場合、経済発展を一段上に推し進めていくうえで必須の産業は果たして育つのだろうか」。
「輸出産業が育つまで暫時国内産業を保護下に置くことは、必要ではないか」。
「世界銀行は金融セクターの改革に関し、あまりにも市場メカニズムに重きを置きすぎてはいないか。優遇金利で融資を行うある種の開発銀行を持つことは、むしろ福祉を増進する上で大切ではないか」。
「民営化にはそれなりの前提条件が必要で、効率一点張りはいかがなものか」。
これらはいずれも、海外経済協力基金(OECF、現在、日本輸出入銀行と統合し、日本国際協力銀行)が「オケージョナルペーパー第1号」として発表した論文 から抜き出したものである。
一見して明らかなように、市場の開放と市場メカニズムの貫徹、規制の撤廃を求めたワシントンコンセンサスに対し、主として性急さをとがめるという形式によって、批判を加えたものである。
今読み直すと批判の口ぶりにどこかおじけたところがある。しかしこれですら、当時は内外の関心を大いに浴びた。およそ日米関係に関心を持つほどの米国人は、みな日本がこのような批判をなしたことに驚きを隠さなかったものだ。
当の日本側もこれが前代未聞の珍事となることを十二分に予想し、「世界銀行の主要なる出資者の一員」という資格をことさらに強調することで、批判の正当性を自己弁護しようとしていた。
アメリカによる世界経済支配の終焉
http://tanakanews.com/e0108thai.htm
2004年1月8日 田中 宇
2003年8月、タイ政府は1997年の通貨危機からの「救済策」としてIMFから借りていた資金を、予定より2年前倒しで返済し終わった。このことは、タイの人々にとってナショナリズムの高揚につながる出来事だった。タイの国営テレビでは、タクシン首相が巨大な国旗の前に立ち「わが国は、二度と国際金融資本の餌食になることはない」と誓いを立てる姿が放映された。タイ内外のマスコミは「タイはようやくアメリカの経済植民地から独立した」などと報じた。
タイがアメリカの「経済植民地」だったというのは、誇張した表現ではない。タイ人の中のかなりの部分は、1997年の通貨危機と、その後IMFによる「救済」に名を借りた締めつけ策が、アメリカによる謀略だったと考えている。
市場が比較的開放されていたタイは、通貨危機が起きる前、アメリカが推奨する自由主義の経済政策を実行する優等生国の一つだった。金融格付け会社も、タイの国債に対して高い評価を与えていた。冷戦後、アメリカは「市場は開放されているべきだ」「財政赤字はない方がよい」「国営企業は民営化されるべきだ」「規制は少ない方がいい」といった「市場原理」主導の経済政策の原則を打ち出し、自国と世界各国がこれを守るように求めていた。タイは「ワシントン・コンセンサス」と呼ばれるこの原則を守っていた。
この原則は、冷戦が終結しつつあった1989年に世界銀行のエコノミストだったジョン・ウィリアムソンという人が最初に提唱した。当初は、中南米諸国の経済の不安定さを改善するために考えられたもので、世界銀行やIMF、米財務省など、ワシントンにあった経済関係の諸機関がこの政策を守る方向で合意したことから「ワシントン・コンセンサス」と呼ばれた。
当時はちょうど、ソ連崩壊でそれまで社会主義陣営にいた国々が、ソ連からの経済援助と経済政策の指針を失い、困っていた。アメリカは、世銀やIMFを動かしてそれらの国々に資金を提供する見返りに、ワシントンコンセンサスを遵守せよと要求した。
通貨危機発生の後、タイ政府はIMFに緊急融資を頼んだ。1997年7月、IMFの担当者たちがタイにやってきたとき、タイのマスコミや野党系の人々らは「これで、無責任で無能なわが国の政治家、財界人、高官たちにお灸が据えられ、浪費や愚行が改められるだろう」と期待し、IMFを歓迎した。ところが、その1カ月後、IMFがタイ経済を改善するためと称して打ち出した政策は、タイの人々の期待を裏切るものだった。
IMFは、危機前からの高金利政策を維持するとともに、政府支出を大幅に削ることを要求した。高金利は外資が逃げないようにするための政策だったが、同時にタイ国内の企業の資金調達を難しくしてしまい、不況に陥ったタイ経済をますます冷え込ませる結果となった。
政府支出の削減の方は、ほとんどプラスの効果がない政策だった。タイは危機の前年まで財政は黒字で、むしろ不況時には政府の支出を少し増やし、民間経済が冷え込んだ分を政府部門の支出で補う政策が望ましかったのに、IMFが打ち出したのはその逆の方針だった。財政赤字の削減は、ワシントンコンセンサスの一般的な「教義」には合致していたが、通貨危機後のタイに適用すべき政策ではなかった。
加えてIMFは不良債権を抱えたタイの金融機関の即時閉鎖と、外国資本がタイの金融機関の株を買えるようにする施策を求めた。タイ政府は、外国勢に株を買ってもらうのではなく、タイ国内で強い銀行と弱い銀行を合併させ、もっと弱い銀行は一時的に国有化するという、昨今の日本と同じ方式で金融危機を乗り切ろうとしたが、IMFはそれを拒否した。
IMFは、通信、エネルギー、交通などの公益部門の企業を民営化し、タイ企業を外資が買収することを制限している規制も撤廃せよとタイ政府に要求した。タイの国会は、外国の金融機関がタイの金融機関の株を100%持っても良いとする法案を可決させられた。
こうした展開をみてタイの人々が疑い出したのは「通貨危機はアメリカの金融機関、金融当局と投機筋が組んで、タイの主要企業を乗っ取り、経済成長の果実を吸い取るために仕組んだ出来事だったのではないか」ということだった。アメリカ側からは、タイの人々の疑いを裏打ちする発言も出てきた。たとえば1998年2月、通商代表だったバーシェフスキーが米議会で「タイの公益企業が民営化されれば、アメリカ企業が買収できるチャンスが高まる利点がある」と発言している。