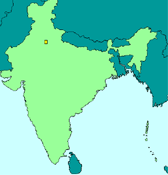失敗百選
~ボパールでのイソシアン酸メチル放出(1984)~
http://www.sydrose.com/case100/shippai-data/308/
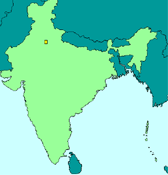
【事例発生日時】1984年12月2日
【事例発生場所】インド マッディヤプラデーシュ州 ボパール
【事例概要】
インドのボパールにある UCIL(ユニオンカーバイドの子会社)で農薬の
セビン製造プラントの保全工事中に、パイプラインを
洗浄した水と農薬の中間原料であるイソシアン酸メチル
(MIC)のホスゲンとの反応がきっかけでMICの重合反応が
起こり、MICタンクに亀裂が入って、 毒性の強いMICが大量に漏洩した。
付近の住民を中心に、死者約3,400人、
負傷・傷害者約20万人という大惨事が生じた。
そのほかに、3,000頭の牛が死んだとか、 40km2にわたって草木が枯れたというレポートもある。
なお、MICの重合およびMICの水との反応を
防ぐために、MICには微量のホスゲンが含ませてある。
【事象】
インドのボパールにあるUCIL (ユニオンカーバイドの子会社)で農薬のセビン製造プラントの
保全工事中に、毒性の強い農薬の中間原料であるイソシアン酸
メチル(MIC)が大量に漏洩した。
付近の住民を中心に、死者約3,400人、
負傷・傷害者約20万人という大惨事が生じた。
【経過】
1978年、UCILのボパール工場で事故発生
(1983年までに計6件の事故発生)。 1979年、1978年の事故後、親会社のUCLは、
調査団を送り、調査の結果数々の不備な点が明らかになった。
1980年~、ボパール工場でイソシアン酸メチル
(MIC、メチルイソシアネート)を本格製造するようになって米国から運ぶ必要が
なくなり、それに伴ってはMICの貯蔵量を少量とするよう管理責任者が提案した
(MICの使用量は5トン/日)。
しかし、西ドイツやオランダ等では禁止されていたMICの大量貯蔵タンク
(40トン3基)は継続使用された。
1981年、安くてより安全な新農薬が
市場に出回り始めたこともあり、ボパール工場の業績悪化。
経営の合理化が進められ、装置の保守や従業員の教育・訓練はなおざりになり、
オペレーターは半数に削減され熟練技術者の離職も進んだ。
運転マニュアル上は、専任の安全責任者1人、監督者3人、オペレーター12人を
1シフトとしてプラントに配置することになっていたが、人員削減により
1シフト6人とし、責任者と監督者は1人ずつ、夜間は保守の責任者1人がいる
だけになった。
1981年12月、有毒ガス漏洩事故が発生した。
1982年5月、1981年の事故後、UCLから再度事故
調査団が送られ、タンクからの漏洩、粉体爆発の可能性、安全弁や計測装置の不良
など10項目の安全管理上の欠陥が指摘されたが改善されなかった。
しかし、UCILはUCLには1件を除きすべて改善と報告、UCLもチェックしなかった。
1984年7月、米国ウエストバージニアのUCLプラントで
安全調査がされ、MICタンクの暴走反応を防ぐための対策を講じて米国環境保護局に
報告したが、海外子会社であるUCILには知らせなかった。
1984年10月22日~、MIC製造プラントを保守点検のため休止。
休止前に、保守点検を容易にするため、ジャンパーラインを増設して安全弁排出ヘッダと
工程排出ヘッダを接続した。
11月30日、MICを中間タンクから窒素を使って
反応槽に移送しようとしたが、バルブの欠陥により(推定)、タンクの圧力が上がらなかった。
しかし、原因の調査はしなかった。
12月1日、再びMIC移送しようとしたが失敗。
2日(日曜)、MICプラントの責任者(MICを扱っていないプラント
から転任)は、タンクの圧力が上昇しないのはパイプ内の汚れが原因と誤判断し、
パイプラインの水洗浄を指示した。
21:30~、水洗浄の際、安全弁からのMIC漏洩防止
のためのスリップブラインド(金属シート)を挿入して他のシステムから
遮断することが安全マニュアルに定められ、1981年のUCL社の安全調査でも指摘されていたが、
実施しなかった。
オペレーターはパイプラインの洗浄が十分ではないことを責任者に報告。
この間にパイプライン中に水が溜まっていった。
暫く中断後、洗浄再開。パイプラインに溜まっていた水がジャンパーライン
を通って工程排出ヘッダに入り、更に、バルブを通ってMIC中間タンク中に入った(推定)
一方、MIC精製蒸留塔の運転が粗雑だったため、MICとホスゲンの分離が不充分になり、
ホスゲンを多く含むMICができたが、製品分析をしていなかったため、
製造したMICをオフスペックタンクに入れるべきところを、中間タンク内に入れていた。
このため、中間タンク内でMIC中のホスゲンと水が反応し塩化水素発生。
これが鉄製の安全弁排出ヘッダと反応して塩化第二鉄を生成し、
タンク内に入った鉄イオンがMIC重合反応の触媒として作用(推定)。
安全弁排出ヘッダは、MICによる腐食を防ぐため、安全マニュアルではステンレス製と
するように定められていた。
MICタンクは安全マニュアルで0℃維持を定められていたが、冷却装置は6、7月から作動しておらず、常温のMICタンク内で重合反応進行し、内部温度が250℃以上(推定)に上昇し、圧力上昇。タンク内温度が5℃に上昇すると作動する警報装置はリセットされておらず不作動状態であった。
23:00頃、現場のオペレーターがMICタンクの圧力が通常の2~3psiから10psiに上昇したのを確認したが、よくある計器類の故障と思い、異常事態が発生しているとは考えず、圧力降下用の空タンクへのバルブ開放をせず、交替した次のオペレーターにも圧力上昇を伝えなかった。
23:30頃、安全バルブ(40psiに設定)が壊れ、MIC漏洩。
オペレーターは催涙刺激と臭気でMICの漏洩に気付いた。
23:45、オペレーターはMIC漏洩を監督者に報告したが、
漏洩は月に1度程度は起きていたこともあり、お茶の休憩後に対処することにした。
作業員一同で休憩中、MICの漏洩が増加し、タンク周辺にガスが充満した。
3日00:45~、タンク内圧力が55psigでスケールアウトし、
タンクのコンクリートカバーに亀裂が発生し、バイパスラインから流れ込んだMICが
高さ33mの燃焼塔の高さから、大気中に大量(約55トン)に噴出し、周辺に拡散した。
付近の住民を中心に、死者約3,400人、
負傷・傷害者約20万人という大惨事が生じた。
【原因】
大事故となった原因は大きく分けると、
1.MICの異常な重合反応、2.事故防止あるいは事故拡大防止システムの欠如、
3.人的問題の3つになる。
MICの異常な重合反応、
パイプラインの洗浄でパイプラインに溜まっていた水が
ジャンパーラインを通って工程排出ヘッダに入り、更に、
バルブを通ってMIC中間タンク中に入った(推定)。、
一方、MIC精製蒸留塔の運転が粗雑だったため、
MICとホスゲンの分離が不充分になり、ホスゲンを多く含むMICが
できたが、製品分析をしていなかったため、
製造したMICをオフスペックタンクに入れるべきところを、
中間タンク内に入れていた。
このため、中間タンク内でMIC中のホスゲンと
水が反応し塩化水素発生。これが鉄製の安全弁排出ヘッダと反応して
塩化第二鉄を生成し、タンク内に入った鉄イオンがMIC重合反応の
触媒として作用してしまった(推定)。
事故防止あるいは事故防止拡大システムの欠如
まずMICタンクは安全マニュアルで0℃維持を
定められていたが、冷却装置は6、7月から作動しておらず、
常温のMICタンク内で重合反応進行し、内部温度が250℃以上
(推定)に上昇し、圧力上昇した。
また、タンク内温度が5℃に上昇すると
作動する警報装置はリセットされておらず不作動状態であった。
さらに、ボパール工場でMICを本格製造する
ようになって米国から運ぶ必要がなくなり、それに伴っては
MICの貯蔵量を少量(5トン/日)とするよう管理責任者が提案した
にもかかわらず、MICの大量貯蔵タンク(40トン3基)は継続使用された
ことは事故を大きく拡大してしまった。
人的問題、
事故当時、経営合理化のため大量のレイオフもあって
従業員のモラルが著しく低下していた。
そのため数々の安全マニュアルの無視が行なわれた。
そのベースにはMICの危険性に対する認識不足、
安全思想の欠如が存在したと考えられる。
このことは、オペレータがMICタンクの圧力上昇を計器の故障と
誤認したり、MIC漏洩を受けた監督者が、その処置をお茶の時間の後
にするといった行為、さかのぼれば、この大事故以前のUCC本社の
査察結果の指摘を無視した。
さらには、UCC本社の海外子会社への技術移転に対する基本的考え方にも
疑問がある。
【対処】
MIC漏洩の12月3日0:50ごろ、消防隊がMICを水吸着するため
燃焼塔へ放水したが、燃焼塔が高く、水が届かなかった。
また、MIC中和のため排出ガススクラバの運転を開始しようとしたが、
スクラバ内にはMICを中和するためのアルカリはなかった。
ボパール工場は駅やバスターミナルに近接していたこともあり、
多数の不法居住者が工場近くで生活していた。
非常を知らせるサイレンも1:00ごろまでならず、工場の周辺で眠っていた人々に
被害が出始めた。 異常を察知した州政府当局が1:15に工場に問い合わせたが、
工場側は何も重大なことは起こっていないと答えた。
12月4日、同日までにMICにより1,120人の死者が出て、
約12,000人がハミディア病院に向かったが、同病院の収容能力は750人であった
ため、病院はパニック状態となった。
UCILは漏洩したガスの性質、また何のガスに暴露された場合の
手当て方法について一切情報を与えなかった。
【対策】
本事故の半年後、親会社UCCが米本国インスティチュートで
類似の事故を起こしたため、対策にやっきになった。
まず、米国化学工業協会(CMA)が事業所周辺の地域社会との
コミュニケーションを緊密にすることを狙って自主的な行動指針(CAER)を
作ったが、連邦政府や一部の州政府は法規制に乗り出し、1986年に連邦環境省は
「緊急時計画および地域社会知る権利法」(SARA TitleⅢと呼ばれている)を制定した。
主な内容は、
州知事が州緊急自体対応委員会(州委員会)を組織し、
緊急事態計画立案区域を指定し、地域緊急事態計画立案委員会
(地区委員会)を組織させる。
地区委員会は計画対象施設を確認する、それは以下など。
地区委員会は緊急事態対応計画を作成し、行使する(訓練も含める)。
州/地区委員会は公衆に対し情報公開を図る。
このために地域公開情報閲覧場を開設し、マスメディアにその旨
を広告する。
事業者は②の該当施設を地域委員会に届け出る。
などである。
また、1992年に労働省が「高度の有害化学物質に対する
プロセス安全管理規則」を公布した。
その内容は、
プロセス危険分析を行い、それに基づいて必要な対策の
実施計画を立て文書化し、実行する。
その前にプロセス安全情報を集め編集する。
操作手順書、保安検査計画、危険作業実施手順書を作成し、実行する。
設備を適切な方法と周期で検査・テストする。
新設設備・変更設備の操業開始前の安全確認。
従業員に対する教育、訓練の実施。
などである。
【背景】
ユニオンカーバイド社(UCL)は、多様な化学製品を生産しており、
1984年当時、世界40カ国で営業、従業員10万人、世界第7位の化学会社であった。
子会社のユニオンカーバイドインド社(UCIL)は、
元々乾電池を製造していた。農業振興をしようというインド政府の要請により計画され、
1974年には、殺虫剤製造の工業許可をインド政府から取得した。
その工場建設に当たり、UCLは故障時の責任を負わないという契約を
結び、1人いたUCL社員も後に帰国してしまった。
1977年、インド独自での操業と完全自給を目指して、
ボパールでMIC製造装置建設、MICをベースにした殺虫剤の製造を開始した。
1978年~、MIC製造装置が計画通りに運転できなかったため
改修を余儀なくされた。
1980年に、ボパールにMIC製造工場を設立、MICの製造を再開した。
1982年~、MICを原料に農薬セビンの製造を開始していた。
1978年から1983年にかけてボパール工場で6件の事故が発生していた。
1978年の事故発生後および1981年の事故後UCLは調査団をインドに送り、
ボパール工場の安全チェックを行い、タンクからの漏れ、粉体爆発の可能性、
安全弁や計測装置の不良など数々の不備な点が指摘されていた。
しかし、不具合による工場稼働率の低迷や、
安価な別系統の農薬が市場に出るなどして、1981年には収益ゼロ、
1984年には400万ドルの赤字などで、経営の合理化が進められ、
装置の保守や従業員の訓練がなおざりにされていた。
1984年当時は、従業員1万人、インド21位の企業であった。
UCLは50%以上の株を保有していた。
【知識化】
事故防止システムが幾重に用意されていても、
そのシステムが設計通り機能しなければ、事故は起こる。
システムとして構築した計器類などのハード面と従業員の
教育などのソフト面との両面を維持しなければならない。
利益優先の合理化は、保守点検レベルを低下させ、計器の誤動作を
日常化し、大きな事故のきっかけを作る。
化学プラントは各プロセスにおける危険分析を行い、
それに基づいて必要な対策の実施計画をあらかじめ作成
しておくことが大切である。
化学プラントの地域への情報公開とコミュニケーションを密にし、
防災訓練などで万一の際の対応に備えておくことが大切である。
本質安全の考えで設計する。もしMICがなければ、漏洩もしなかった。
またMICの量が適切であれば、こんなに大きな被害にはならなかった。
【総括】
この工場は、MICを大量に貯蔵・使用していたにも関わらず、
経営の合理化を優先し、装置の保守や従業員の教育をほとんどしていなかった。
そればかりか、MIC漏洩事故を何度も繰り返しながら、何の対策も講じないまま
操業を続けていた。
海外進出に際し、現地人化や現地の独自性は尊重すべきではあるが、
こと安全性に関しては、本社の海外子会社に対しての危険物管理の対策、
技術の現地への十分な移転が不可欠といえる。
もっとも、本事故の半年後の1985年に親会社UCCが
米本国インスティチュートで類似の事故を起こしており、グループ全体での
安全に対する認識が低かったと判断される。
以上