下記の構造を有する化合物。医薬品・香料などの合成原料。
2003.9.9 発表
■超臨界CO2を利用したフェノール水素化技術の開発に初めて成功
● ポイント
概要
独立行政法人
産業技術総合研究所【理事長 吉川弘之】 超臨界流体研究センター【センター長 新井邦夫】白井誠之有機反応チーム長は、超臨界二酸化炭素溶媒と担持ロジウム触媒の組み合わせにより、フェノールからシクロヘキサノールとシクロヘキサノンを従来技術より低温で且つ高効率に得る合成技術を開発した。この技術は、触媒劣化が起こらないのでその長期使用が可能であること、有機溶媒を使用しないため合成後の生成物の蒸留分離工程を必要としないなどの特長を有する。更に二酸化炭素は反応後に気体として回収し再利用が容易で、環境負荷を低減する製造システムとして実用化が期待される。
超臨界流体研究センターでは水と二酸化炭素の超臨界流体を利用した環境調和型有機合成プロセスの開発研究を実施している。今回、超臨界二酸化炭素と担持ロジウム触媒を用いたフェノールの水素化反応技術を検討し、フェノールを効率よく水素化でき、例えば55℃条件下、フェノール転化率100%でシクロヘキサノンとシクロヘキサノールの混合物(KAオイル)が得られた。また圧力制御(二酸化炭素と水素圧)によってKAオイルの組成を制御をできることも明らかにした.シクロヘキサノールはナイロン66、ポリウレタン等の、シクロヘキサノンはナイロン6の中間原料として用いられている。これまでのフェノール水素化によるKAオイル製造では、担持パラジウム触媒を用い、反応温度130〜180℃と高温で行っている。このため、KAオイル製造中にパラジウム金属触媒表面に炭素質が堆積し、触媒が劣化しやすい欠点があった。触媒寿命の向上化と反応器に投入する熱エネルギー削減の観点から、反応を低温で進行させることが検討課題となっていた。本合成技術では従来技術に比較して大幅に(100℃以上)反応温度を低下させることが可能となった。このことにより触媒表面上への炭素質の堆積が起こらず。触媒寿命が飛躍的に向上し,何度でも触媒を繰り返し使用できることや連続使用が可能となった。更に有機溶媒を使用しない環境負荷低減技術であることも優れた特長と考えられる。
固体触媒と超臨界二酸化炭素溶媒を用いる有機合成技術は、有害な有機溶媒の使用削減のみならず、溶媒である二酸化炭素を反応後に容易に除去可能なことから生成物分離工程が簡略化できる利点もある。すなわち超臨界二酸化炭素を利用した水素化技術はKAオイルの製造のみならず種々の不飽和化合物の水素化反応など、化学工業やファインケミカルズの分野での応用が期待されている。
従来から知られている実験結果との比較
フェノールを水素化してシクロヘキサノンおよびシクロヘキサノールを合成する手法は、主に欧州で用いられている。現在は主に担持パラジウム触媒を用い、反応温度130〜180℃,反応圧力0.1〜0.2MPaの条件でフェノール転化率ほぼ100%、シクロヘキサノン選択率97%、シクロヘキサノール3%である。本プロセスは反応温度が高い欠点を有する。
今回得られた知見では、超臨界二酸化炭素溶媒と担持ロジウム触媒を用いることによって反応温度55℃及び転化率100%でフェノールを水素化できる。水素圧と二酸化炭素圧のみの制御によりシクロヘキサノールとシクロヘキサノンの選択率を制御できる利点を有する。
本合成技術は以下の点で従来技術よりも優れている。
用語の説明
◆フェノール
下記の構造を有する化合物。医薬品・香料などの合成原料。
![]()
◆フェノール水素化反応
1個のフェノールのベンゼン核に4個の水素原子(2個の水素分子)が付加してシクロヘキサノン得られる。
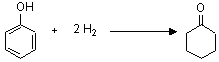
1個のフェノールのベンゼン核に6個の水素原子(3個の水素分子)が付加するとシクロヘキサノールが得られる。
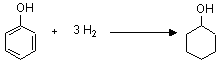
フェノール水素化反応は逐次反応でシクロヘキサノンとシクロヘキサノールの両方が得られる。
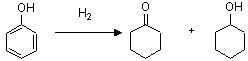
◆シクロヘキサノン
ナイロン6の中間原料に用いられる。
![]()
[戻る]
◆シクロヘキサノール
アジピン酸、ナイロン66、ウレタン等の中間原料に用いられる。
![]()
[戻る]
◆KAオイル
シクロヘキサノンとシクロヘキサノールの混合物であり、KAオイル自体もアジピン酸、66ナイロン、ポリウレタンの中間原料として用いられている。[戻る]
◆KAオイル製造プロセス
現在以下の3プロセスが稼動している。
(1)シクロヘキサン酸化プロセス:シクロヘキサンを空気酸化してKAオイルを得る方法。
(2)シクロヘキセン水和プロセス:ベンゼンの部分酸化によりシクロヘキセンを合成し、ついでシクロヘキセンを水和させてシクロヘキサノールを製造する方法。旭化成が開発。
(3)フェノール水素化プロセス:フェノールを直接水素化してシクロヘキサノンとシクロヘキサノールを生成する方法。主に欧州で用いられている。現在はシクロヘキサンよりフェノールの方が安価になっており、プロセス的に有利となっていると考えられる。[戻る]
◆ナイロン6,ナイロン66
ポリイミド系合成高分子繊維の総称がナイロン。名称代表的ナイロンがナイロン6とナイロン66である。引っ張り強度、耐薬品性、染色性に優れているため衣料等広く用いられている。[戻る]
◆担持金属触媒
ロジウム、パラジウム、白金などの貴金属粒子の表面は触媒作用を有する。金属を固体触媒として用いる場合、単位グラムあたりの触媒活性向上と熱的安定性構造のために、微粒子化し活性炭、シリカ、アルミナなどの高表面積を有する多孔体に担持して用いる。多孔体に金属微粒子を担持した触媒を担持金属触媒という。例えばロジウム金属を担持した場合は担持ロジウム触媒という。[戻る]
◆超臨界状態
物質の状態(気体、液体、固体)は圧力と温度によって決まる。液体状態の物質の圧力と温度を上げていくと、液体と気体が共存する2相状態へと変化し、最終的に気体とも液体とも性質を異にする1相の状態になる。この状態を超臨界状態という。超臨界状態になる最低の温度と圧力を臨界温度、臨界圧力という。二酸化炭素では臨界温度は31.1℃、臨界圧は7.38MPaである。[戻る]
◆不飽和化合物
分子内に炭素原子と炭素原子の間の二重結合などの不飽和結合を含む有機化合物。付加反応、重合反応などを起こすため、化学原料の多くは不飽和結合を有している。[戻る]
2004/3/5
東北大学多元物質科学研究所/新日鐵化学
世界初、超臨界二酸化炭素を溶媒としたε-カプロラクタムの低温合成プロセスの開発に成功
―イオン性液体を触媒としたグリーンケミカルプロセスの開発―
http://www.nscc.co.jp/download/040305.pdf
東北大学多元物質科学研究所(所長:中西八郎)と、新日鐵化学株式会社(社長:西恒美)は、超臨界二酸化炭素を溶媒に用いることで、50℃程度の低温度条件下においてシクロヘキサノンオキシムからε-カプロラクタムを合成する化学プロセスの開発に、世界で初めて成功いたしました。
今回のプロセス開発は、東北大学の横山千昭教授、喬焜助手が中心となり、新日鐵化学が反応プロセスの最適化および実用化のための課題評価などにおいて協力したもので、東北大学および新日鐵化学の共同により特許を出願しています。
ε-カプロラクタムは、ナイロン6の原料となる工業的に重要な物質であることから、従来より、様々な合成法が研究開発されており、最近では、400℃程度の高温度下で固体触媒を用いた気相合成法や、380℃程度での超臨界水を溶媒とする合成法などが注目されています。
しかし、いずれの合成法も、かなりの高温条件が必要であり、触媒寿命・触媒再生や生成物の分離回収などに技術的課題が残されていました。
今回開発した方法は、新規に開発した酸性を示すイオン性液体を触媒とすることにより、室温付近(50℃程度)という、従来法に比べ、極めて低い温度下での反応の進行を可能とした点が大きな特徴であります。さらに、反応生成物であるε-カプロラクタムの抽出分離溶媒として、超臨界二酸化炭素を用いることで、通常の有機溶媒では分離が困難であった、イオン性液体からのε-カプロラクタムの分離回収を、高効率で行えることを実証した点に独創性があります。
また、今回開発したプロセスは脱有機溶媒を目指したグリーンケミカルプロセスであり、東北大学では触媒として用いたイオン性液体を再利用するプロセスについても、すでに実証しています。
今後は、現状では不明となっている、今回開発した酸性のイオン性液体を触媒とした場合のカプロラクタム合成経路を明らかにすることによって、イオン性液体の分子構造と反応活性の関係など、反応のメカニズムを解明し、より反応活性の高いイオン性液体の開発を進めていくとともに、反応装置・分離装置の最適化、プロセス全体の経済性の向上に関する研究をさらに進めることで、本プロセスの実用化を目指してまいります。