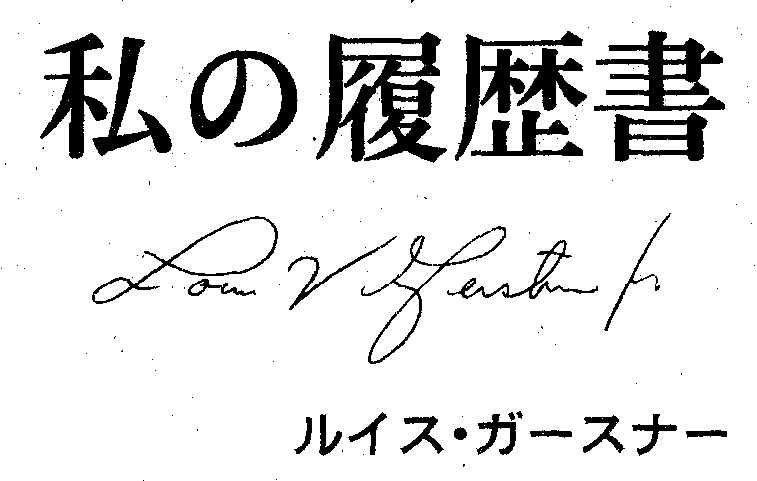
(日本経済新聞 2002/11)
Louis V. Gerstner, Jr.
その2
ナビスコヘ
10年に一度のポスト CEO就任後に資産急落
アメリカン・エキスプレスの社業拡大に成功して、1985年に社長に昇進した。マスコミはひんぱんに私を次期会長兼CEO(最高経営責任者)の有力候補に取りざたしていた。だが88年、私が46歳の時、会長は5歳ほど年長で、まだ十分若かった。彼とは社業の多角化戦略をめぐって意見の相違があった。このままでは私が会長になる目はほとんどないと思われた。
89年4月1日、米ビジネスウィーク誌が「10年に一度の美人コンテスト」と呼んだRJRナビスコ社の会長兼CEOのポストに就いた。同社は大手菓子メーカー、ナビスコ社とR・J・レイノルズ・タバコ会社が合併してできた大企業で年商170億ドル、全米の優良企業調査で9番目にランクされていた。
この会社の合併劇は現代米国産業史の中でも最も壮大な冒険というべきものだった。相手先の資産を担保に借金をして買収するLBO(レバレッジド・バイアウト)方式で、いろんな投資会社がこの会社を手に入れようと、入札合戦を繰り広げていた。最終的にはコ−ルバーグ・クラビス・ロバーツ社(KKR)というベンチャー・キャピタル企業が落札し、その後まもなくへッドハンターを使って私を探し出し「この会社をうまく軌道に乗せてほしい」と、ばく大な負債を抱えた新会社の経営者に据えたわけだ。
私自身はこの花嫁争奪戦を丹念に追っていたわけではなかったが、新聞で新会社のトップ選びが「10年に一度あるかないかの大きなポスト」と書きたてるのを見て、「よし、アメリカン・エキスプレスのCEOになれる見込みが薄いなら、アメリカで今、最も挑戦しがいのある仕事に就く機会を見逃す手はない」と考えた。それが転身の理由だった。
RJRナビスコは単一の会社ではなく、合併の結果、企業文化も管理制度も異なった会社が4、5社寄せ集まった親会社だった。消費者相手のビジネスはアメックス・カードの発行事業である程度わかっていた。企業財務についてもマッキンゼー社の財務部門の責任者だったのでかなり理解できた。それにハーバード・ビジネススクールにいたころやりたいと思っていたブランド商品の経営管理ができると期待もした。ナビスコの主力である菓子部門の商品のほとんどは市場シェアが1位か2位だった。
だが実際には、ブランド管理ができたのは就任してほんのわずかの時間だけだった。ほとんどの時間は資産の売却、負債の軽減、現金の調達、負債返済計画の練り直しに費やされた。負債総額は260億ドルに上り、発展途上国の負債額より多く、換算するとフィリピンのすぐ下、モロツコより上で10位にランクされると評されていた。
最初の数カ月、何とか会社を軌道に乗せ、社業を発展させていくめどがつきそうだった。そこへ突然、LBO市場が崩壊する事態が起きた。LBOも当初は堅実な資金手当てで行われていたが、そのうちにジャンク・ボンド(信用度の低い高利回り債)で資金調達するようになっていた。ジャンク債市場は高成長が見込まれ、年21%もの高利で取引されていた。わが社もジャンク債を大量に抱えていた。そのジャンク債市場が暴落したのだ。このため手持ちの資産価値が急落して、債務を返済するのに当初予定よりはるかに多く3倍もの資産を売却せざるを得なくなってしまった。
ナビスコを去る
財務状況改善に忙殺 「経営は株主とともに」知る
1980年代後半には「日本の脅威」論が盛んだった。日本は何事もうまくやっているのにアメリカはすべてに失敗している、米企業は時代の変化に対応できず、起業家精神に劣り、実効ある動きもできない、などと議論されていた。
そこに登場したのが、効率の悪い企業を分割し、所有者が経営者となって非公開企業のように経営しようという考え方で、これが相手先の資産を担保に買収するLBOブームをもたらした。たくさんの老舗、眠っていた会社がLBOで変身し、再活性化したのは確かによかったと思う。
RJRナビスコ社を買収したKKRも非常に有能な会社で、LBOでいくつも成功していた。だがどんな打者でも10割は打てない。RJRでは期待した結果が出なかった。89年から93年にかけて、私は全く新しい難題の山に埋もれていた。複雑極まりない上に大変な債務を抱えたバランスシートをいかに改善するかに忙殺されていた。後から考えれぱ、KKRは買収に金を払い過ぎたのであって、その後の4年間は資産売却しながら社業全体の秩序をどう保っていくかという厳しい競争だった。
それは何ともすさまじい場面の連続だった。最初の12カ月で110億ドルもの資産を売らなければならなかった。大変な数の債権者・債務者会議があるし、前の経営者たちの冗漫な出費を一掃しなければならなかった。例えば「RJRナビスコ・チーム」名で32人もの陸上選手に高給を払っていたのだ。
それは辛い毎日だった。私は事業を解体するのではなく発展させたかったのだ。ただし、どんな仕事をしても学ぶことはある。この時の経験で、事業にはいかに現金が大切か、キャッシュ・フローがどれだけたっぷりあるかが企業の健全経営の最も重要な指標になるということを骨身にしみて理解することができた。
また企業の経営と所有の関係についてもより深くわかった。KKRではCEO(最高経営責任者)が自分で金を払って市場で自社株を大量に買わない限り、ストック・オプション(自社株購入権)を与えていなかった。そこで私はRJR株を最終的に240万株所有し、260万株以上のオプションを得ていた。
その体験から、経営者が株主と緊密に連携することがいかに重要であるか、それもリスクを伴わずにストック・オプションを与えるような方式ではなく、経営者が直接会社を所有するように自分の金を注ぎ込む方式で株主になることが望ましいとよくわかった。この考えは私がIBMに持ち込んだ経営哲学の重要な部分にもなっている。
92年にはRJRナビスコの社業は順調だったが、LBOで所有者たちが期待しただけの見返りがないことは明らかだった。それでKKRが抜け出したがっているのが見え、KKRにスカウトされた私もそうすべきかと考え始めてはいた。
ただ私はあと1、2年はとどまるつもりだった。会社を真にブランド商品だけで競争できるよう変身させたかったからだし、92年末までは転職する意図などなかった。そこへ突然、IBMの話が舞い込んできた事情は、この連載の2、3回目で紹介した通りだ。
RJRを離れた時、同社の株価は低迷していて、私は財テク面では成功しなかった。だが金の問題ではない。大事なのは将来への挑戦ということだった
IBM初日
本社の第一印象「官庁」幹部に我が経営方針説く
IBMのトップ交代は1993年3月26日に発表された。その記者会見はニューヨークのホテルで朝9時半に始まった。登壇すると、40人近いカメラマンが押し寄せた。会見中、絶え間なくフラッシュを浴びながら、自分の人生が決定的に変わったことを実感した。
アメリカン・エキスプレスでもRJRナビスコでも注目は浴びていたが、ここは全く違う。私が公的な存在になっているのだ。IBMは単なる大会社ではなく、世界的な制度なのであって、その一挙手一投足を克明に、世界から監視されている。私が大変な挑戦をする様子を、まるで金魚鉢の中にいるように周囲から見られているのだ。IBMのCEO(最高経営責任者)とは大統領や議員のような公職と同じなのだとわかった。
記者会見の後は社内会議だ。マンハッタンからヘリコプターで北へ50キロほど離れたニューヨーク州アーモンクの本社に飛んだ。その第一印象は忘れられない。まるで官庁だった。長い、静まり返った廊下が延々と続く。美術品の展示もなければ、コンピューター会社らしい雰囲気もない、会長室にはコンピューターもなかった。
大会議室に案内され、そこで主要幹部50人ほどの経営会議メンバーと会った。男性は全員が申し合わせたように白のワイシャツ。私一人がブルーのシャツで、違和感があった(その次の同じ会議では私が白ワイシャツを着て出ると、全員がカラーシャツで出席していた)。
私は儀礼的なあいさつではなく、40分ほど演説した。まず、この職を引き受けたのが自分で望んだのではなく、米国の競争力を高め、米国経済を健全なものにする使命を帯びて請われて来たことから始め、当面の課題を話した。
「IBMが世間でいわれるように官僚主義的なら、早急に改めよう。政策決定の中央集中主義はできるだけやめよう。ただし、その分権化は中央の戦略、顧客本位主義とのバランスをとりながら進めよう。人が多すぎるなら早急に適正な規模まで減らそう。それも半年後には済まそう」
「IBMは社員を解雇しない」と公約するのはやめよう、とも言った。実際、すでに90年から12万人近い社員が自発的に、あるいは半強制的に辞めているのに、会社は「解雇なし」政策というごまかしに固執していた。
ここで私が話した中で最も重要なのは体制の戦略に関する点だったろう。当時、業界関係者もIBM首脳陣も一様にIBMを分割すべきだと語っていた。私は「そうかもしれないが、そうでないかもしれない。わが社には総合的な商品、サービスを提供する独自の優れた能力があるのではないか」と問いかけた。後から思えば、私は着手する前から、この会社を細切れにする戦略に懐疑的だった。
私は自分の経営方針として「プロセスより原則重視」「悪い情報を隠すな」「敏速に動け。急ぎ過ぎて間違えるのは、遅すぎて間違えるよりいい」「会議は最小限に減らせ」ーーなどを明示した。
さらに最初の90日間の最優先事項と当面30日間の課題を提示した。各事業部門の責任者には顧客の要望、競争力の分析、技術的な諸問題、今後1、2年の展望と重要課題などについて10ページのリポートを提出するよう求めた。
兄の助言
生え抜き、社内に精通 「メール・システム活用せよ」
1993年4月1日が私の正式なIBM生活の始まりだ。午前6時45分にコネティカット州グリニッジの自宅に社有車が迎えに来て、ニューヨーク州北部に散在するIBMの施設の一つに連れて行った。海外事業部門の総責任者会議に出席するためだ。
長大な会議室には海外領地に君臨する王侯貴族たちが勢ぞろいして卓を囲み、その後ろには若い幹部たちが2列に並んで控えていた。諸侯がそれぞれ自国の事業を短く報告するのだが、背後に控えた連中が忙しくメモを取り、主君に手渡す。まるで米連邦議会の公聴会のようだった。
彼らが社内でも栄誉あるAA(アドミニストレイティブ・アシスタント)と呼ばれる役員補佐だと教えられた。IBMでは何百人もの中・上級幹部にAAが配置され、有望な若手管理職の中から抜てきされるという。AAは段取りを調整し、メモを取り、ボスの動きに目を配り、時には秘書業務もする。それが出世の登竜門とのことだった。だがそんな仕事でビジネスの厳しさを学び、指導力を養う訓練になるとは思えなかった。
最初の2週間は直属の部下である役員たちとの打ち合わせ、新しいCFO(最高財務責任者)や人事担当責任者の候補となる人たちとの面接、主要施設の訪問に忙殺された。中でも最も重要な面談が2日目にあった。兄のリチャードに社内状況を説明してほしいと頼んだのだ。
3歳年上の兄は大学を出てすぐIBMに入り、スピード出世していた。重要な欧州とアジア地域の役員を務め、本社の重役候補だった。ところが悲運にも、これから本領を発揮するという時に原因不明の病気で倒れ、それが鹿を媒介にするライム病とわかって半年前に入院治療のため退社せざるを得なかった。だが役員たちが顧問として復帰するよう望み、主力製品のメーンフレームをどうすべきかを検討する役員と一緒に仕事を続けていた。
社会人として別の道を歩んできたが、家族が集まる時にはいつも再会を喜ぶいい話し相手だ。出世に関するライバル意識などは一度も持ったことがなかった。とはいえ、兄が会長室に入って来た瞬間、痛々しい思いがした。病気にさえならなかったら、兄がこの会長のいすに座っていることも十分あり得たからだ。
兄はきわめてよく準備していて、誰よりも優れた洞察を示す報告をくれた。特にメーンフレームはもう死滅するという議論を否定し、パソコン戦争に勝つことに全勢力を投入すべきだという当時のヒステリックな思い込みに真っ向から反対した。
さらに「兄からの助言」と書いたメモをくれた。いわく「オフィスと自宅にパソコンを置いて社内電子メール・システムを使え。前任者はやらなかった」「近視眼的な提案や縄張り争い、背後から刺す手口には公然と反対しろ。どれもIBM社内の得意技だ」「お前の言動は社の内外で一つ一つ克明に分析され、それぞれ勝手に都合よく解釈されることを自覚しておけ」「心から信頼できる助言者を何人か見つけろ」「母さんに電話しろ」−−。
社内には監観グループがいて、私が兄を後見役に迎えるかどうかを興味津々で見ていた。私はそれが兄のためにも、私のためにもならないと判断した。兄とはその後も話をしたが、いつも短時間で済ませた。
社員・顧客・株主
十字砲火の株主総会 社内に広がる喪失感知る
1993年4月15日、本部以外の施設を初めて訪ねた。慎重に考えた末、ヨークタウンの研究所に決めた。ここがIBMの魂の故郷で、コンピューター産業を生んだ技術開発の知的宝庫だったからだ。技術は私が当面、最も弱い部分だ。研究者たちが私を指導者として受け入れてくれるだろうか。ナビスコ出身なので社内では「クッキー・モンスター」と呼ばれていた。
大ホールのステージに立った。客席はすべて埋まり、演説は会場に入りきれず食堂にいる社員にも、世界中の研究施設にも同時中継された。重点目標を掲げ、スピード、顧客本位、チームワークを強調し、苦痛を早急に過去のものにしようと訴えたもので、その後、一貫した公約になった。IBMの将来に研究開発がいかに重要かを強調した。同時に顧客と研究者がもっと緊密になり、IBMの革新的な製品開発能力をもっと生かして、人々の本当に重要な緊急課題を解決する方策を探る努力をしようと呼びかけた。拍手はあったが、技術者たちが何を思っているかはわからないままだった。
最初の1カ月で最も精神的に傷ついたのは4月26日、フロリダ州タンパで開催された年次株主総会だった。株価は87年の43ドルから当日12ドルまで下落し、前年の株主総会当日に比べても半額以下だった。
いらだたしげに集まった株主は2300人。壇上から見ると会場は白髪の海で、IBM株を持ってフロリダで引退生活を送っている人たちがたくさんいることが一目瞭然だった。私はもうしばらく我慢するようお願いする一方、敏速に必要な改革をすべて断行し、本来の姿に戻すことを約束した。儀礼的な拍手の後、十字砲火が始まった。株主が次々に立って会社を非難し、最前列に座っている取締役たちに矛先を向けた。まさに血祭り。取締役会メンバーの一人一人がやり玉に上がり、直撃弾を浴びた。株主たちは早急な業績回復を望む以外、容赦がなかった。それは実に長く、ぐったり疲れる総会だった。
翌日、欧州に飛んだ。欧州・中東・アフリカを担当するトップたちと会うためで、フランス、イタリア、ドイツ、英国を1週間で回った。夜明けから深夜まで業務報告を受け、社員集会で話し、顧客を訪問した。この地域の事業は44カ国で9万人以上の従業員を抱え、総売り上げは90年の270億ドルをピークに下降し続けていた。
この旅行で学んだ最重要のメッセージは内部事情についてだった。組織のあらゆるレベルで不安感、自信喪失が広がっており、特に社内の煩雑な手続きが問題の原因であり、これをうまく改革すれば問題も解決できるはずだという思いが広く流布していた。
出社した最初の週から、私は「同僚の皆さんへ」と社員向けの手紙を会長室のパソコンで送り始めた。圧倒的に肯定的な反響が多く、励ましの返信は私を慰め、支え、エネルギーの源になった。同時に率直で大胆、ぶしつけなメールもたくさんもらった。
「たわごとを言わず、ちゃんと仕事しろ。半年ごとに人をゴミみたいに捨てるようなことはするな」「うわさでは、あなたが現場視察する時にはどこを通るかまで入念に計画し、通路の壁は塗り直し、真新しいじゅうたんが敷かれるそうですが、本当ですか」
意識改革
幹部に顧客訪問指示 形式的な経営委員会廃す
1993年4月末、経営会議を開いた。CEO(最高経営責任者)就任を発表した日に出席したトップ50人から成る会議だ。就任3週間で感じたことを話し、積極的に評価できる点もあるが、顧客の信頼を失っていること、会社がやみくもに分社化の方向に走りすぎていることなどの問題点を指摘した。そして「顧客抱きしめ作戦」を提案した。
幹部50人全員が3カ月以内にそれぞれの最重要顧客を5カ所訪問し、その要望や不満を親身になって聴き、適切な対策を取る。各人が直属の部下である部長クラス(合計200人以上になる)にも同じことをさせる。訪問1件につき1、2枚の報告書を私と顧客の問題を解決できる者に届ける、というものだ。これで顧客がIBMとは交渉しにくいというイメージを少しでも減らしたかった。訪問する顧客数は5件に限らず、多ければ多いほど得点が増えることにした。
この作戦はIBMの企業文化を変える第一歩となった。会社を立て直すには外部の力を得て、顧客の求める方向に持っていくことが重要だということを社内に浸透させたかった。これが社内に波紋を投げかけ、私が本当に報告書をすべて読んでいることがわかると、急速に動きが良くなり、反応も敏感になってきた。
経営会議と同じ日に経営委員会(MC)もあった。これは私を含めて6人の首脳会議で、従来、毎週1、2回、一日がかりで大量の報告を聞くものだった。主要な決定事項はすべてこの委員会に上がり、この委員になることがIBM全幹部の究極の目標になっていた。だが、これこそIBMの硬直化を象徴するものと私には映った。形は中央で統制しているようだが実は責任もリーダーシップも拡散し、あいまいなシステムだ。
MCは本来、有力な部門が提案することに他の有力幹部が疑問を呈し、論争することを制度化して生まれた。当初は革新的な手法だったのだろうが、時が経ると、そのシステムを利用して、いかに自分たちの主張を通すかに腐心するようになる。1990年代初めには事前合意のシステムに変わってしまっていた。スタッフが幹部抜きで、できるだけ下から全社的に合意を取り付けるやり方だ。当然、MCが目にするのは下からあちこちで妥協した結果である単一の提案でしかなかった。
この妥協案をつくるプロセスで調整役を担うのがAA(役員補佐)のネットワークだとわかった。中国の宦官のように、実際の権限や責任をはるかに超えた強大な力を振るっているのだ。MCの使命は単に形式を整え、AAの言いなりに承認の判を押すことだけなのだ。
その最初の会合で私は「この組織は続かない」と言った。政策決定にもっと個人的に関与したかったからであり、何より、委員会が決定することに居心地の悪さを覚えたためだ。そして、過去数十年にわたってIBMの経営システムの中枢だったMCは事実上、93年4月をもって死滅することになった。
当時、重要会議といえば、担当幹部が図表を大画面に映し説明するのが決まりだった。ある時、私はそのプレゼンを途中で遮って映写機のスイッチを切り、「何をすべきかを議論しよう」と言った。これが全く予期せぬ大きな効果をもたらした。その日のうちに話がメールで世界中を駆けめぐり、大騒ぎとなったからだ。
メーンフレーム
大幅な値下げ決める 各社のCIOと思い共有
IBMが目先だけでも持続可能かどうかは主力製品であるメーンフレ−ムにかかっていた。利益の90%以上がこの大型サーバーとそのソフトの販売から来ていた。メーンフレームの運命は会社の運命であり、どちらも石のように急速に沈みつつあった。
そこでまずこの事業部門の実情を聞いた。過去15カ月間、売り上げが落ちているだけでなく、市場シェアが崖を転がるように急落していた。理由を聞くと「日立、富士通、アムダールがわが社より30−40%も安値で出荷していますので」と言う。当然「なぜわが社も値下げで対抗しないんだ」と聞くと、答えは「値下げしたら、売り上げも利益も大幅に減ってしまいます」だった。
会社が意識的にか無意識にか、主力製品S/390の甘い汁を吸い続けようとしていて、それによって死への道を歩んでいることがはっきりわかった。私は直ちに「高値押しつけ」戦略をやめ、2週間後の顧客会議で思い切った値下げを発表できるよう営業戦略を練り直せ、と指示した。
1993年5月18日、私のIBM時代の中でも最も重要な会議になった「顧客フォーラム」を開催した。全米の主要大企業175社近くのCIO(最高情報責任者)が集まった。彼らこそ最も大切な顧客であり、IBMの存亡は彼らにかかっていた。夜、何人かと一緒に食事した。
彼らはIBMが「メーンフレームは死んだ」という神話が広がるのを放置している、と怒っていた。パソコン信者たちは、これからのIT(情報技術)インフラは銀行も航空会社も電力会社もデスクトップ・コンピューターで間に合うようになるとマスコミに吹聴し、信じ込ませている。だが彼らCIOはそれが事実ではないことを知っていた。
メーンフレームの価格設定がひどいことにも憤慨していた。IBMが官僚主義的で、顧客企業の社内の異なったシステム同士、あるいは米国本社と海外事業所のシステムを結ぶ統合システムづくりがきわめてむずかしいことにもいらだっていた。
翌朝、私は事前に用意した原稿を捨てて、心から思っていることを即興で演説した。まず顧客あってのIBMであること。顧客の意見に耳を傾け、顧客の求めるものを提供すること。CIOたちの怒りや不満は私がIBMに来る前の体験に照らしても、全くその通りだと同意した。そしてメーンフレームを大幅に値下げすることを約束した。
メーンフレームのセットは当時、6万3千ドルだったが、7年後にはわずか2500ドルと、実に96%も価格が安くなってきた。
この値下げ計画が、おそらく他のあらゆる計画よりもIBMを救うことになった。
短期的には、値下げしなければ得られるはずの収入、利益が減って破産する危険があった。もしこの戦略がうまくいかなければ、私はこの王国を明け渡す最後の皇帝となるところだ。しかし幸い、計画はうまくいった。処理能力に換算したメーンフレームの全出荷量は、93年に前年比で15%落ちたものの、94年には41%増に転じ、その後は95年に60%増、96年47%増、97年29%増、98年63%増、99年3%増、2000年25%増、01年34%増と驚くほど好転した。
決断−解体せず
武器は規模と幅広さ 支出減らし社内体制改革
最初の3カ月で顧客、従業員、業界関係者らと意見交換した後、私は1993年夏に4つの重要な決断を下した。第一がIBMを分割せず、一つの会社として統一させていくということだ。いつ、そう決めたのかははっきりしないが、この判断はIBMにとっても、私の職業人生の中でも最も重大な戦略的な意味を持つものだった。私はIBMの規模と幅広さとが際だった競争力になり得ると語ってきたし、IBMがさまざまな技術を統合する先駆者となるなら、素晴らしい価値を持ち得ると考えていた。
そこで各事業部門でそれぞれ別個に進んでいる分社化、独立採算制への動きはエネルギーと金の膨大な無駄遣いであると、すべて中止した。それに対し、幹部陣の反応は複雑に分かれた。これで会社が救われると見る人たちは歓喜し、沈没するタイタニック号から自分の救命ボートとなる事業部門を切り離そうとしていた人たちは失望した。
第二の決断は財政面の根本からリストラ(再編成)することだった。わが社の収支バランスはすべておかしくなっていた。収入は主力のメーンフレームに依存し過ぎ、その売り上げも、粗利益も値下げ競争で落ちている。沈没を避けるには利益の落ち込み以上に支出を大幅に減少させなけれぱならない。
財務部門が収支比率を試算した結果によると、同業他社が1ドルの収入を得るのに平均32セント支出しているのに対し、IBMは42セントも費やしていた。収入総額に換算すれば70億ドルもの冗漫な出費をしていることになるのだ。
そこで、まず1株当たりの配当を2.16ドルから1ドルへと半減させた。そして支出を89億ドル節減することにした。このため3万5千人の雇用を減らさざるを得なかった。苦痛だが、選択の余地のない生き残り策だった。
第三に、多国籍企業の中でも史上最大規模のリエンジニアリング計画に取りかかった。IBMの組織全体で事業のあり方について全面的な見直しが必要だと考えたからだ。10年がかりの改革となったが、あらゆる社内管理体制が変わることになった。
着任した当座、私はIBMなら内部で世界最高のITシステムを活用していると期待していた。ところが事実は全く違った。内部システムは老朽化していて、システム相互の情報交換もできなかった。在庫から会計、業務遂行、配送にいたるあらゆるシステムが旧来のシステムから突然変異のように生まれたもので、24事業部門の個々の必要に応じて、つぎはぎ細工で適応させたものばかりだった。
IBMのCIO(最高情報責任者)は今は一人だが、当時はCIOの肩書を持つ者が128人もいて、それぞれ自分の部署のシステム設計に責任を持ち、専用ソフトをつくる予算も持っていた。こうしたIT支出を95年末までに20億ドル節減し、155カ所のデータセンターを16カ所に整理し、31系統あった社内通信網を1つに統合した。
第4に着手したのが非生産的な資産を売却し、キャッシュを増やすことだった。93年にIBMがいかに現金不足で倒産寸前だったかを知る人はほとんどいないだろう。社用機の大部分を売り、全米各地にある高層ビルを売り、所蔵美術品を競売にかけ、遊休地を8千エーカーは売却した。
地球規模の経営
分野別にチーム編成 目標共有、部門間交流促す
とりあえず消火作業をした後は、この会社の基本戦略を再構築しなければならない。その戦略は、私の信念に基づいて「IBMには顧客のためにあらゆる部分を統合する能力がある」という、他にはまねのできない独自の強さを生かすものにしたかった。
だが顧客のために統合力を示す前に、まずIBM自身を統合しなければならない。IBMは政府を除いて世界でも最も複雑な組織だろう。単に規模が大きい(2001年の売上高が860億ドル)だけでなく、地理的に広範囲にわたる(160カ国以上で営業している)からでもない。
IBM独特の複雑さは二重にある。第一にあらゆる組織、ほぼあらゆる個人がIBMの既に顧客であるか、これから顧客になる可能性を持っており、地球上のいかなる組織、いかなる産業、いかなる政府に対しても、その大小を問わず顧客として対応する用意をしていなければならない。
第二に情報技術産業界では技術の変化の度合いとスピードがきわめて速いことだ。商品の寿命はかつて10年くらいあったが、今ではせいぜい9カ月か10カ月にまで短くなっている。科学的な新発見によって事業計画や営業見込みがたちまち崩れてしまうことがひんぱんに起きるのだ。
その結果、IBMでは地域単位の領土ががっちりと固まってしまう一方、製品部門の力が強大になっていた。各地域が縄張りを守ることを優先し、地域内で発生する注文などはすべて自分たちだけで丸抱えしようとしていた。技術部門も自分たちが必要と思い、欲しいと思う研究施設や生産ラインをつくることに熱心で、顧客のニ−ズに応えて顧客優先で仕事することなどほとんど念頭になかった。
そこで私はこの閉鎖的な領土制を打ち壌すべく宣戦布告した。地球規模で産業分野別にチーム編成することを決めた。顧客を政府、銀行、保険、流通、製造業など12分野に分け、それぞれの担当グループが予算と人事を掌握する、と宣告した。これには各国責任者たちが直ちに「決してうまくいくはずがない」「会社が壌れてしまう」などと予想通り、激しく反発してきた。
訪欧の折に、欧州地域の社員たちは私が定期的に世界中の社員あてに出しているEメールを受け取っていないことが偶然わかった。調べてみると、欧州地域の総責任者がメール中継センターでストップさせていた。本人に理由を聞くと「一連のメッセージはわが社員には不適当。翻訳するのがむずかしい」と言う。
翌日、本人をニュ−ヨーク本社に呼びつけ、社員は彼のものではなくIBMの社員であり、私からのメッセージは決して妨害してはならないと言い渡した。彼はしかめ面をし、不機嫌そうに出ていった。間もなく、彼は会社を辞めた。
同時に私は部門間の交流を促すため世界経営会議(WMC)を創設した。メンバーは35人で年に4、5回会って2日間、各事業部門の動向や全社的な課題について討議するものだ。ここで私が期待しているのは、わが社の重役チームが一丸となって共通の目標に取り組むことであり、主権国家の集まりである国連のように、それぞれが自分の国益を主張することではない。経営幹部たちがお互いの腕をつかんで「素晴らしいアイデアがあるので、ぜひ君に手伝ってほしいんだ」と言い合うようになるのが狙いだ。
ブランドの統合
強さの原点アピール 広告予算、役員裁量なくす
IBMを救う努力も、もしIBMというブランドが崩れてしまったら無に帰してしまうだろう。成功する企業とは顧客本位、市場本位でしかも強力なマーケティング組織を持たなければならないものだと私は常に信じてきた。だから世界企業をつくる第二歩としてIBMのマーケティングカの強化に取り組んだ。
IBMは1980年代、テレビCMでたくさんの賞を受けた。だが90年代初めには広告宣伝が無秩序状態に陥ってしまった。分社化の動きの中で、あらゆる事業部門がそれぞれ勝手に専属の広告代理店を雇い、93年には70社以上の代理店がばらばらに活動していた。業界誌のある号ではIBMの広告が18種類も出て、そのデザインも、メッセージも、さらにはロゴマークまでも異なっていた。
93年6月、私はコーポレート・マーケティングのトップにアビー・コーンスタムを雇った。彼女とはアメリカン・エキスプレス時代に何年も一緒に仕事した。この仕事が重要かつ急を要するため、私のやり方をよく知っていて、私が一言えば十わかってくれる人材がほしかったからだ。
IBMにはそれまでマーケティングの本当の責任者がいなかったから、どの事業部門も最初、彼女を無視しようとしていた。IBMは技術と営業の上に乗っかった会社であり、マーケティングが大事な業務と見なされず、経営的にも軽視されていた。そこでアビーに60日間かけて実態調査するよう命じた。
その調査で、社業の不振が大きく報道されていても、IBM商品全体のブランド・イメージはまだ強力であることがわかった。顧客はIBM製品が優れていると信じて買っている。私が予想した通り、わが社の一番の強みは製品群全体に対する統一したイメージであって、個々の製品の良し悪しではなかった。それゆえ、顧客がなぜ一元的なIBMと契約したがっているのかを明確に打ち出すのがマーケティングの目標となった。
その第一段階は、役員たちから広告予算を取り上げ、自分の好きな代理店を使っていつでも好きな時に広告を出すぜいたくをやめさせることだった。それまでは重要な業界誌に全くIBMの広告が載っていない月があるかと思えば、翌月には大量のぺ−ジに登場して、まるで特別号スポンサーのような印象を与えていた。特に年末の11、12月には予算を使い切ろうとした大量出稿が目立っていた。
アビーの仕事はそうした広告費の使い方、広告メッセージを統制することだった。彼女は広告代理店を1社に絞った。それも全世界的に。各地域の幹部の猛反発にも動ぜず、94年に「小さな惑星へのソリューション(解決策)」をテーマに新しいキャンペーンを始めた。そのテレビCMはチェコの尼僧からパリジャンまで国際色豊かな人たちが話す現地語に英語の字幕がつき、大好評だった。IBMがグローバルに活動し、統一的なサービスの提供者として世界第一級だというメッセージを再確認するものとなった。
広告宣伝予算を全面的に見直し、統合することで相当な節約ができたが、われわれは直ちに広告宣伝への投資額を倍増し、予算規模はその後も維持している。続くキャンペーンでは「eビジネス」という言葉を打ち出し、IBMがIT業界の重要な流れを決める指導者であることを定着させてきた。
ネットワーク
パソコン支配終えん 無秩序な業界構造と決別
1990年代初め、産業界で先行したのは皆、パソコン関係の企業だった。パソコンメーカーのデル社、コンパック社もいたが、圧倒的な強さを示したのはデスクトップのOS(基本ソフト)を押さえたマイクロソフト社であり、マイクロプロセッサーをつくったインテル社だった。
そんな中でIBMは、コンビューター時代を切り開き、業界の最も重要な技術を発明した実績を持ちながら、自分の築いた地位がデスクトップ業界に毎日どんどん侵食されているのを眺めているしかなかった。多国籍企業や大学、世界各国政府が使っているシステムを構築した人たちが、ワープロやコンピューター・ゲームを提供する人の後塵を拝している。これは何とも気まずい、腹立たしい状況だった。
IBMは80年代にパソコン事業を始めたが、製品化にはあまり熱心ではなかった。パソコン市場の規模や重要性を過小評価していたためだ。結果として、コスト面でも新製品を市場に提供するスピードの面でも、世界最高級のパソコンを生産することができなかった。
私がIBM在職中、最も修復困難だったのがパソコン事業部門だ。過去15年近く、パソコンからはほとんど収益があがらなかった。1台売るたびに赤字が増えていた時期で、売り上げが落ちるのが悪いニュースなのか、朗報なのか判断に苦しむほどだった。
人生は何事も運次第だが、IBMでは二度、幸運に恵まれた。一度目は93年にデニー・ウエルシュに会えたことだ。IBM勤務が長く、サービス部門の責任者をしていた。二度目はインターネットが到来し、われわれがネットワークの世界に大きく賭けたことだった。
デニーは大柄で気さくな笑い上戸で、仕事熱心だった。元飛行士で空軍将校だったが、IBMでは政府のアポロ宇宙船計画などの高度技術システムの構築を担当し、69年にアポロ11号が月面着陸に成功した時にはケープケネディのコントロール室にいた。
初めて二人だけで会った時に彼は、顧客のために最もふさわしいコンビューターシステムの設計、構築から日常業務としての管理、運営に至るまで情報技術のあらゆる面を駆使して顧客向けの代行サービスを提供する姿を望ましい会社像として描いてくれた。
私の心も熱く燃え上がった。彼の描いたイメージこそ、私がIBMの顧客だった時代に求めていたものだったし、IBMを統合させようという戦略にピタリと合致するものだったからだ。今や顧客は自分たちがいろんなコンピューター会社、ソフト会社から部品やソフトをバラバラに購入して自分で組み立てて使わなければならないという業界の構造にいら立ちを募らせている、と私は確信していた。
95年11月13日、ラスベガスで開催された業界最大の見本市、コムデックスで私は最初の重要な基調講演をした。その主要部分は、コンピューターの世界ではパソコンの支配が終わり、ネットワーク中心の時代がやって来るというものだ。「過去15年間、パソコンは個人にとって素晴らしい道具でした。しかし皮肉なことに、パソコンは人間が最も人間らしく振る舞う点には、あまりよく適合しないのです。お互いに意思疎通をし、一緒に働き、お互いにやり取りし合う関係には必ずしも適していない」と私は言った。
「9.11」以後
会社として社会貢献 社員らの犠牲精神に誇り
IBMの9年間、私は社員に数百通のメモや手紙を出してきた。特に2001年9月11日の悲劇的な事件のような緊急事態が発生した際には、たくさんのEメールを出した。その一部を紹介しよう。
(9月11日午後5時7分送信)
「同僚の皆さんへ。本日の破局的な事件に対して個人として、組織として、できることはたくさんあります。個人としてはまず献血の呼びかけに応えられるでしょう。ですが、最も重要な貢献は会社としての行動です。この種のテロ攻撃の目的は社会を混乱させ、マヒ状態に陥れることです。これまで数時間、主要な顧客から業務上の支援を求める声がたくさん寄せられ、担当チームがその対応に大車輪で動いています。私たちは破壊されたインフラを復旧・整備するという重要な組織的役割を担っているのです。私たちにできる最善の方策は、要請があれば直ちに応じられるよう準備を整え、手際よく敏速に行動することです。数時間前にも書き送りましたが、職務を果たすには注意深く、しかも最良の判断を下すよう心がけてください。最後に、私たちは今、被災地にいる同僚の安否の確認作業を全力で続けています。私たちの仕事は24時間態勢で続きます。その進展状況は逐次、連絡します」
(9月13日午後1時17分送信)
「顧客支援の状況を伝えます。世界貿易センターと周囲2区画四方にはIBMの顧客が1200社以上あり、そのうち数百社はすでに私たちと接触しています。現在、20件は非常事態を脱し、業務再開を果たしています。私たちは大容量のデータ処理センターを提供し、破壊されたデータ処理施設を再構築し、顧客の業務部門をIBMで肩代わりする応急措置をとっています。……世界中の社員から何百通ものメモが私の所に来ています。その全部には返事できませんが、全部ちゃんと読んでいます。皆さんが事態を憂慮して何か自分にできることはないかと言っていることに私は深く感動しています。社員が心配して自己犠牲の精神を発揮していることを私は誇りに思っています。集中して、共に行動しましょう」
(9月21日午前11時41分送信)
「IBMは9.11救済基金に500万ドル寄付したのに加え、基金のインターネット上の管理運営を直ちに引き受けました。これまでの寄付総額は1億ドルを超えています。この10日間、IBMは100万ドル単位の金と数千時間の労力を投じて大惨事からの復旧作業に取り組んできました。95年の阪神大震災のときもそうでしたが、IBMが顧客からも同僚からも地域社会からも最も必要とされる時に、社員の皆さんは常に雄々しく立ち上がっています。私は今ほど皆さんの同僚であることに誇りを感じるときはありません」
私は企業が成功するのは、社会が健康で生き生きしている時だけだと信じている。顧客や社員たちが丈夫でいられる地域社会が企業に必要だからだ。同時に企業には単に寄付金を出すだけではない重要な役割があるし、社会のために他の誰よりもうまくできるものがある。だからこそIBMの構造改革を進める中で慈善事業の哲学も見直し、社会問題を解決するのにわが社の技術を活用しようとするように努めてきたのだ。
日本及び日本人
動き速くなった企業 経営者、世界に引け取らず
日本はマッキンゼー時代以来、私の仕事上の重要な部分を占めている。1970年代初めには何度か来日して日本支社の開設を手伝った。当時の日本は高度経済成長の盛りを迎えようとしていた。
70年代後半から80年代前半にかけてはアメリカン・エキスプレスが日本でのプレゼンス(存在感)を非常に高めた時だ。私も社の幹部として再三訪日しては日本航空や邦銀とクレジツト・カードや旅行小切手について交渉した。RJRナビスコ時代も日本での事業展開に取り組んだ。
同時に日米欧三極委員会のメンバーとなり、当面の国際的な課題や政策を議論した。そこで当時の国連難民高等弁務官、緒方貞子さんという素晴らしい人に出会えたし、日本企業のトップや高級官僚とも知り合うことができた。
IBMは日本人を顧問としてではなく取締役会の正式メンバーに加えている数少ない世界企業だ。97年以来、社外重役を務めてもらっているベン・マキハラ(槙原稔三菱商事会長)とはもう15年来の親しい付き合いで、私の親密な相談相手でもある。
私は日本の大企業、特に家電、自動車、情報技術、鉄鋼などのメーカーが実に革新的なことに最大級の敬意を払ってきた。最近では流通部門で一流デパートが高品質のサービスを提供していることに感心している。店の商品の並べ方から客を居心地良く迎えるやり方など際立っている。
日本は教育が非常に良く行き届き、洗練され、同質的な社会だと思う。日本人は勤勉でよく仕事し、お金をためている。特に高度成長期の日本は政府、産業界、政治家、取り締まり当局などすべてがきわめてうまく絡み合っており、「日本株式会社」と呼ばれるほど、国全体が一つの見事に統制のとれた企業体のように動いていた。
その後、経済的にも社会的にも、さらには政治的にもいろんな問題が起きてきたことは本紙読者の方が私よりはるかに詳しくご存じだ。そして日本人たちはこれまで統一的な解決策を待っていたのだろうと私は思っている。
70−80年代に私が折衝した日本企業は、米企業に比べて意思決定が遅かった。だが過去5年ほどは日本企業の多くが敏速に動き、意思疎通を率直にし、透明度が高くなり、決定が速くなっている。優れた経営者たちが「自分の問題は自分で解決する。国全体が動き出すのを待ってはいられない。国際的な競争力を高めるために必要な手をどんどん打っていく」と言い始めている。
そこが今の日本の素晴らしいところだと思う。CEO(最高経営責任者)として優れた日本人たちと一緒にゴルフし、酒を酌み交わし、仕事する中で、彼らの多くはどこの国の経営者にも全く引けを取らないと私は考えている。
日本IBMは北城格太郎会長、大蔵卓麻社長という優れた指導者によって経営が実にうまくいっている世界第一級の子会社だ。私がもし何か重要な国際的な課題に取り組むのに6−8人規模のトップを集めるとしたら、北城さんはまずその一人に入るだろう。それと椎名(武雄日本IBM最高顧問)さんは特別な人で、非常に感度が高く、愛国心と愛社精神に満ちあふれた人だ。彼と一緒に過ごす時間はいつも実に面白く、深い洞察に富んでいるものだった。
指導者の条件
勝つことに情熱傾注 後任者選考の上位条件に
組織を変革する最も重要な要素は指導者だ。優れた組織とは管理運営されるものではなく、指導者によって導かれているものだ。勝つことに情熱を燃やす個々人の努力で常に達成レベルを上げていく組織なのだ。
優れた指導者は生産性の高い文化を生み出す。高い目標を設定し、結果を公平に評価し、きちんと説明するので、皆が安心して従っていける。どの競争相手よりも早く新しい環境に組織を適応させ、前進させていく変革者である。指導者は組織の誰からもよく見えていなければならない。優れたCEO(最高経営責任者)は自ら腕まくりし、進んで問題に取り組む。担当者たちの後ろに隠れ、他人のやった仕事を管理するだけの人間では断じてない。トップは毎日、顧客からも、取引相手からも常によく見える存在でなければならない。
指導力はコミュニケーション能力でもある。率直に、頻繁に、しかも喜んで相手の知性に敬意を払いながら正直に意思表示していくことが重要であり、自分の真意をあいまいにごまかす表現、二枚舌は決して使うべきではない。
そして何よりも、指導力には情熱が不可欠だ。偉大な指導者は古今東西を問わず、勝つことに情熱を傾けてきた。彼らは毎日、毎時間、勝とうとして仲間を駆り立てている。ハーバード・ビジネススクールの教室で「情熱」という言葉を聞いた記憶はないが、優れた経営者は全員、強烈な情熱を持ち、それを示し、情熱を愛しているものだ。
そもそも悲観論者のために仕事したいと思う人がいるだろうか。自分の会社の弱点ばかりあげつらい、愚痴をこぼしている管理者のために働きたいと思う人がいるだろうか。われわれは皆、勝者のために働きたい、勝ち組に入りたいと思っているのだ。社内のどのレベルの管理職も自分の指導力を高めるために、そうした感情面を重視すべきだと私は思う。
「勝て、実行しろ、チームを組め」−ー私はこの3つの言葉を指導者の条件とし、全IBM社員が目標設定する際の最も重要な規範として提唱してきた。ビジネスは勝つことを目指した競争であり、実行するには速いスピードと効果的にこなせるだけの技量が問題になる。しかも一つの組織として統一的に明快に前進しなければならない。
IBM取締役会が私の後任を選ぶ際、「情熱」が条件の上位にあった。サム・パルミサーノは才能豊かな傑出した幹部だが、彼がIBMを心から愛し、その将来について強烈な情熱を持っているからこそ、私も推薦したのだ。彼は感受性豊かで常に勝つこと、成功のレベルを上げることに情熱を燃やしている男だ。
今にして思うのは、私は常に、そして最後までIBMのアウトサイダーだったということだ。サムをはじめ経営幹部のほとんどは、私と一緒にIBM再生の立役者になったが、彼らは私には決して持ち得ない展望を共有していた。彼らはIBMで育ち、その栄光の日々から苦難の日々、そし回復の過程をすべて体験している。そのルーツは私より深く経験も豊かだ。
サムには伝統の継承という、私が決してできなかったことができる。それは過去に戻るのではなく、過去の最良、最高の部分を基にしながら未来に向けて挑戦し続け、変化し続けることだ。それこそがIBMのCEOの究極の責務なのだ。
引退後のプラン
教育などで社会貢献 中小企業支援、釣り楽しむ
最後にIBM引退後のプランを語ろう。私は今後10年を3つの分野に分けている。第一は社会貫献であり、CEO(最高経営責任者)時代にやりたいと思いながら時間がなくてできなかったことにエネルギーを注ぎたい。対象は2つあり、1つは35年間取り組んできた公教育の改革、もう1つが20年来関心のあるがん治療の研究だ。
私は全米の公立学校の教育レベルを向上させるため全米の知事と産業界のリーダーたちでつくった「アチーブ」という組織の共同議長をしている。今、教師の質を高める全国的な委員会を発足させる準備をしている。優れた人材を確保するための募集方法、労働条件、待遇など具体的な行動計画を提示する予定で、実施されれば教育現場の質を改善できると期待している。
加えて私は全米で最高のがんセンター、スローン・ケタリング記念がん研究所の副理事長も務めている。私の弟もがんで亡くなった。私くらいの年齢(60歳)で親族にがんで倒れた者がいないという人は全米でもわずかだろう。
第ニの分野は、愛するビジネスの世界だ。私は先週、国際的な投資会社、カーライル・グループの会長に来年1月、就任することに同意した。同社は129億ドル以上の資産を運用する非上場会社で、世界第一級の目覚ましい業績を上げている。今は非上場会社にとって実に面白い時期であり、私の経営感覚と経験を生かして、この投資ビジネスをますます発展させていきたいと楽しみにしている。
私はこれまでダイムラー・クライスラーとソニーの2社の顧問をしてきた。ダイムラーは真にグローバルな自動車メーカーを目指しており、ソニーはネットワークの娯楽産業という新時代を切り開くことに真剣に取り組んでいる。どちらもきわめて独創的な会社であり、しかも私は出井(伸之)さんら両社のCEOが大好きだ。だから、この2社の顧問は続ける予定だ。
昨年以来、たくさんの会社から社外取締役にという依頼があったが、すべて断ってきた。正式な取締役会メンバーになる気はない。今後は中小企業を支援するような仕事をしていきたいと考えている。
そして第三の分野が私的な活動だ。もう10年以上、釣りが好きで、アメリカやニュージーランドではマス、アラスカやカナダ、スコットランドではサケと全世界を釣りして回った。たいてい友人と一緒だが、たまに妻とも行く。引退後はもう少し釣りを楽しむ時間をとりたい。家族とのんびり旅行もしたい。ある大学で半年間、考古学や中国史を勉強したいので受け入れてほしいと相談もしている。
私の人生で最も大切なものーーそれはまず第一に家族であり、次に教会、その次が仕事だ。私は「権力」という言葉が嫌いで、自分の望むものとして考えたことがない。私が好きなのは「アイデア」であり、「個性を出す」という言葉だ。自分の考えで主体的に、情熟を持って積極的に取り組む人を尊敬している。駆け引きをし、望まぬ妥協をする政治的人間にはなりたくない。妻もまた、そうした私の将来展望を共有してくれているはずだ。