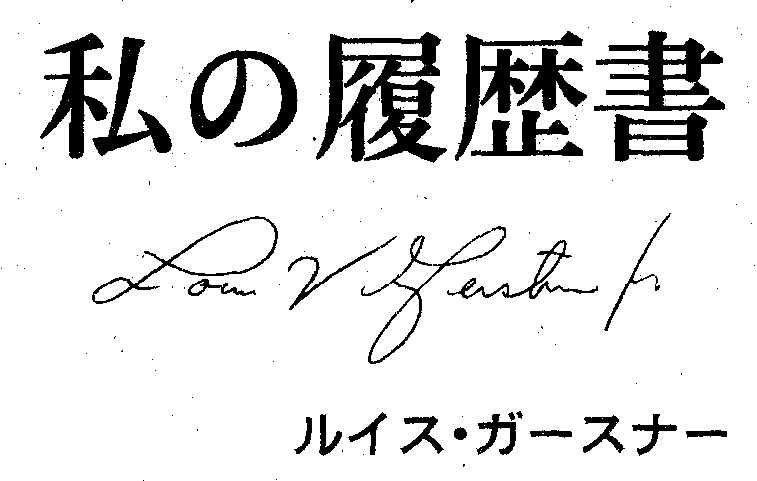
(日本経済新聞 2002/11) Original
Louis V. Gerstner, Jr.
引退発表
生涯IBMマン自負 瀕死の巨象復活で区切り
私は今年末に60歳でIBMを引退する。1993年春、RJRナビスコ会長だった時に請われてIBM会長兼CEO(最高経営責任者)の職に就いてから実に激動の9年間だった。90年代初め、IT革命が急速に進行し国際競争が激化する中で、パソコンからスーパーコンピューターまで抱えるIBMは「瀕死の巨象」と言われ、解体寸前だった。92年の売上高が645億ドルで50億ドルの赤字、全世界に40万人以上いた社員をリストラで30万人までに減らしていた。
そこに私が外部から変革をしにやってきた。その使命はただ一つ、短期目標として「会社を救う」ことだった。率直なところ、就任当時には、この会社を再生させることができるかどうか、たとえできるとしてもどれくらいの期間がかかるかも、わからなかった。実にたくさんのむずかしい決断をしなければならず、会社を望まれてもいない方向に強引にねじ向けることを数多くしてきた。
そしてこの巨象を、大方の予想に反するほどまでに蘇えらせ、復活させることができた。2001年の売上高は859億ドルで純益が77億ドル、社員数も32万人近くまで回復してきた。
私は実社会に出て以来、じっと机に座っていて企業経営を成功させることなどできるはずがないと信じてきた。だからこの9年間、世界中を軽く100万マイル以上飛び回り、何千人もの顧客やビジネス・パートナー、従業員に会い、話をしてきた。そうする中で、私は「正真正銘のIBMマン」になってきたと心の底から感じている。面白いことに、このアウトサイダーがIBMを創業したワトソン親子以外では最も長くCEOの地位に就いていたことになる。
今の心境について、私は引退の決意を発表する全社員向けのEメールの手紙で次のように記した。 「私の当初目標である会社再建は90年代半ばには大筋で達成しました。そうするうちに、私はIBMに恋をしてしまいました。皆さんと同じように、私もこの会社が世界でも最高の職場だと実感するようになったのです。素晴らしくて、大切で、イライラさせられもするし、疲労困ぱいもさせられますが、本当に充実した生活の送れる職場です。私はその瞬問、瞬間を楽しく味わうことができました」
「私の引退時期について、IBMのトップは60歳が定年だからだ、と言う人がいますが、それは違います。そんな年齢制限の規則などありません。私が今そうするのは、タイミングが適切だからです。会社は新しい飛躍を目指しているし、私の後継者となるサム・パルミサーノも満を持しています。私が今ほど会杜の将来について楽観的に、自信を持って見られる時はありませんでした。だからこそ、今が指導者の変わる最適の環境であり、時期であると考えたのです」
「サムはきわめて優れた資質と実績の持ち主ですが、それにもまして彼はIBMの生え抜きです。だからこの会社の性格を核心から把握しています。皆さんが私を支えてくれたように彼を支持してくれることを信じています。私は会長職を去っても引き続きこの素晴らしい会社と、そこで働く優れた皆さんを応援し続けます。なぜなら私は生涯IBMマンだからです」
IBMへの誘い
「大きな挑戦してくれ」 夜の来訪客から熱い依頼
引退を発表すると、米国の有力紙が社説で「ガースナー氏は本を書いたり、ゴルフばかりするより、もっと社会的に有意義なことをすべきだ」と書いていた。面白く読んだが、何千もの手紙やEメールが舞い込んで、「IBMをどうやって救ったか」「企業再生の秘法を教えてほしい」という要望が殺到した。
そうした「一般からの幅広い需要」に応えるためには、まずIBM復活物語を書き、その一方、当分ゴルフに熱中することを控えるしかない。その本は今月中旬、『巨象も踊る』と題して米国で発売される。これは全部自分一人で書いたもので、共著者も代筆者もいない。まず間違いなく私の最初にして最後の著書になると思う。
私の60年の人生の中で、最大の決断がIBMに来ることだった。そこでこの連載もまず、その当時の模様を再現することから始めよう。
それは1992年12月14日の夜のことだった。RJRナビスコ会長だった私はニューヨークに住む大企業トップの常として、意図はいいのだが、まず面白みのない慈善活動のディナーパーティーに出席した。五番街のアパートに戻って5分もしないうちに、一階の受け付けから「バークさまが大至急、今夜中にお目にかかりたいとのことです」と電話があった。夜の十時近くに一体、誰が何用だろうと驚いた。聞けば、同じアパートの上層階に住んでいるジム・バーク氏だという。
彼ならジョンソン・エンド・ジョンソン社の会長としての指導力にも、麻薬追放キャンペーンヘの積極的な取り組みにも深く敬意を払ってきた相手だ。だが個人的にはそれほど親しく付き合っているわけではない。いぶかりながら電話すると、すぐに降りてきて、単刀直入に切り出した。「君がアメリカン・エキスプレス社に最高経営責任者(CEO)として戻るという話があるが、そうしないでくれないか。君にはもっと大きなことに挑戦してほしいんだ」
私は78年から89年まで11年間、アメックス社の経営幹部だったが、辞めてRJRナビスコに移っていた。92年の11月半ばにはアメックス社の重役会メンバー3人がひそかに私に会いに来て、経営トップとして戻ってほしいと要請したことがあったのは事実だった。だが私はその場で丁重に断った。今のCE○は私の強い反対を押し切って誤った路線を歩んだ人だ。その尻ぬぐいをするために後任になるつもりなどない、と。
バーク氏は「近いうちにIBMのトップの座が空くので、就任を考えてほしい」と語った。これには驚いた。IBMが深刻な問題を抱えていることは広く報道されていたが、CE0が交代する話などは全く知らなかった。バーク氏は「どうかIBMから目を離さないでくれ」と繰り返して、引き揚げていった。
翌93年1月26日、IBMはジョン・エイカーズ会長が引退し、後任候補を内外から広く選考するための委員会を設置すると発表した。委員長はバーク氏。彼からは就任を促す電話がすぐに来たが、私は辞退し続けた。
委員会は候補枠を広げ、全米の一流企業トップの名が次々に浮上した。マスコミにはGEのジャック・ウェルチ、アライド・シグナル社のラリー・ボシディ、モトローラ社のジョージ・フィッシャー、さらにはマイクロソフト社のビル・ゲイツの名前まで挙がった。
IBM入り決断
米の宝守るのは責務 選考委の言葉に鼓舞され
1993年2月、新聞、雑誌、テレビは競うようにIBMの苦境を大きく取り上げ、専門家たちはこぞってIBMが生き延びられる可能性は少ない、絶滅寸前の恐竜のようなものだ、と評した。
その間、バーク委員長は私に「今のIBMが求めているのは技術者ではない。幅広い視野で考えることができ、経営を大胆に変革できる強力な指導者だ」と説き続けた。だが私にはどうしても気が乗らなかった。
転機は2月下旬の週末をフロリダの別荘で過ごした時にやってきた。毎日1時間ゆっくりと砂浜を歩いていて心が癒やされているうちに、IBMについても考え直すべきだと思うようになった。RJRナビスコ社の経営が私の意に添わず、辞める潮時だということもあった。
そこで年来の友人で、首都ワシントンで弁護士をしているバーノン・ジョーダンに電話して助言を求めた。彼はRJRナビスコの社外重役でもあった。私がIBM会長候補になっていることも知っていた。バーク委員長が既に彼にも私を説得するよう協力を求めていたわけだ。バーノンはいつものように簡潔に「IBMの仕事を引き受けるべきだ。君がハーバード・ビジネススクールを卒業して以来やってきたことは、そのための訓練期間だ。ぜひ、やってくれ」と勧めてくれた。
2月末、ワシントンで産業人会議があった折、私はひそかにホテルの自室でIBMの会計監査責任者と会い、経理状況を詳細に聞き質した。内情は想像以上に深刻で、IBMが助かる可能性は20%にも満たないことがわかった。
大衆消費財メーカーなら優れた商品さえあれば生き延びられる。だが90年代のハイテク企業では商品が開発され市場でヒットしても、すぐに後発商品に追いたてられ、2、3年で忘れ去られてしまう。これではとてもIBMに未釆はない、と思った。
3月半ば、私はまたフロリダに戻った。自宅近くのヘッドハンターの別荘で、選考委員会の両幹部、バークとトム・マーフィー、それに私の3人だけで会った。
バークは説得にあたって前代未聞の議論を持ち出した。「君が引き受けることはアメリカに対する責務だ。IBMは国宝であり、君にはこの宝を守り、立て直す責任がある」。そう強調し、さらに「ここにクリントン大統領に電話してもらい、彼から直接、就任要請してもらおうか」とまで言った。マーフィーも「IBMの戦略と文化を変革するには君が最適の人材なのだ」と繰り返した。
長い長い午後ぴ最終的に私は「イエス」と言った。なぜそう答えたかはっきりとは覚えていない。たぶんバークの愛国心とマーフィーの「世界第一級の挑戦になる」という言葉に鼓舞されたのだろう。
一人で車を運転して自宅に戻り、家族に私の決断を伝えた。するといつものように反応が割れた。2人の子供は片や賛成し、片や気が狂ったとしか思えない、という顔をした。妻は最初からずっと懐疑的だったが、私の決断を支持し、「素晴らしいことよ」と励ましてくれた。
この時私は51歳の誕生日を迎えて間もなくだった。それからのIBM時代は、この連載の後半紹介する。明日からはそれまでの半生を語ることにしよう。
生い立ち
芯が強い父、軌勉な母 温かい家、礼拝も欠かさず
私は昔から「私的なことを話さない男」とよく言われてきた。それは私生活を大事にするためであり、自分の公的な仕事の世界に私的なものを持ちこむべきではないという信条の表れでもあった。自分の趣味や昔のこと、家族のことなどまず人に話さない。それが今回、IBM引退を区切りに、日本経済新聞杜の熱心な勧めに応じて、60年の人生を振り返ることにした。
私は1942年3月1日に、ニューヨーク州は大西洋に突き出たロングアイランドのナソー郡にある小さな町、ミネオラに生まれた。父のルイスはロングアイランドで生まれ育ち、近くの農揚の牛乳配達のトラックの運転手から始めていろんな仕事をし、地元でも大きな醸造会社の配送課長で定年を迎えた。父はおとなしく、家で仕事の話などまずしない。決して社交的ではないが、いつも.穏やかで、勉強好きで、芯が強く、自分でこうだと信じることは決して曲げない人だった。
母のマージョリーは事務員から不動産販売員をして、最後には地元のコミュニティー・カレッジの事務局幹部になった。非常に気が強くしっかりとしていて、自分にも他人にも厳しく、勤勉だった。子供の教育にも実に熱心で、学校の宿題は必ずちゃんとするようにしつけていた。
私は四人兄弟の二男で、長男のリチャードが3歳年上、三男のジェームズが2歳年下、四男のジョセフは私より10歳下だった。私がなぜ父と同じ名前を付けられたのかは知らないが、米国では二男や三男が父親と同じ名前になることは決して珍しいことではない。
ガースナー家というのはおそらくドイツ系移民の末裔なのだろうが、わが家のルーツははっきりしない。祖父母のころからロングアイランドに住んでいた。両親とも家系を話題にしたことなどほとんどなかった。敬虔なカトリックの家庭で、日曜には教会の礼拝を欠かさず、家の中はいつも温かく、家族でよくまとまっていた。
ミネオラはマンハッタンのペン駅からロングアイランド鉄道で小1時間ほど行った郊外の典型的な中産階級の住む町だった。当時の人口はたぶん数千人。大きな工場もなければ大邸宅もなく、ごく普通のこぢんまりした住宅が立ち並んでいた。
目立ったものとしてはすぐ近くにルーズベルト・フィールドという広大な民間飛行場があり、27年5月にチャールズ・リンドバーグがここからセントルイス号に乗って大西洋横断飛行をしたことで知られるが、それも51年、私が小学生の時に閉鎖され、今では官庁街と大きなショッピングモールに変わっている。
わが家は決して裕福な家庭ではなかったから、家族旅行するような機会はほとんどなかった。上の三人兄弟は年齢も近かったので、ほとんどいつも一緒にいた。裏の空き地でキャッチボールしたり、近所の子供たちと集まっては野球やフットボールをしたりして遊んだ。兄弟で電車に乗ってニューヨーク市内の美術館やプラネタリウムにも出かけた。夏休みには兄弟で一緒に1−2カ月キャンプした。兄弟ゲンカはほんどしなかった。たまにしても、30分もしないうちに忘れて仲直りしてしまう。年の離れた末っ子の子守もみんなでよくやったものだ。
小中高時代
地元の一流校に進む 宿題の後、冒険小説に夢中
小・中学校時代はごく普通の目立たない少年だった。背は高くもなければ低くもなかったし、太ってもやせてもいなかった。それが小学1年生か、2年生の時に1学年上に飛び級した。先生の都合によるもので、当時それほどめずらしいことでもなかった。
公立の小中学校はたいてい面した街路の名前で呼ばれる。私の通った学校はハンプトン学校という名で、創立1906年。町でも最も古い学校で、わが家から歩いて10分くらいの所にあった。学校は8年制で、55年にここを13歳で卒業し、シャミネード高校に入学した。
シャミネード高は1930年に創設された私立のカトリック系男子校だ。当時も今も近隣郡の中でも最優秀校で、生徒の98%が大学に進学していた。入学試験があって、地元の競争率も高かった。
ガースナー家では教育が何事にも優先していて、両親はいつも人生の中でいかに教育が重要かを強調していた。とりわけ母は子供の将来に大変な期待を抱いていた。子供には分け隔てなく接し、私たちが常に最高を目指し、目標を達成し、成功するように仕向けていた。そこで兄弟そろって一生懸命勉強し、一流校に合格すべく準備し、全員が同じ高校に進学した。両親はその学費を都合するために4年ごとに自宅を担保に入れて銀行から借金をしていた。
高校は自宅から4キロほどで、4年間、毎日歩いて通った。私が新入生の時、兄のリチャードが4年生だった。兄とは仲良く、ウマがあった。
シャミネードは人文科学系の古典的な幅広い教養教科を重視している高校で、私はラテン語、科学、数学を4年間、フランス語を3年間習った。また広範囲な読書プログラムがあって、英文学の古典である「ベオルフ」からシェークスピア、ディケンズ、詩集の類までが課題図書になっていた。
私は毎晩3、4時間かけて宿題をこなし、課題図書を読み、それからさらに自分の好きな本も読んでいた。当時、50年代後半の流行作家にイアン・フレミングがいて、そのO07、ジェームズ・ボンド・シリーズに夢中になった。そうした面白い冒険小説は今でも好きで、ジョン・ル・カレの作品は全部、トム・クランシーの作品もたいてい読んでいる。
教科の中では文学、科学、数学が好きで、特に数学ではSAT(適性検査試験)で800点満点を取った。
スポーツに関しては、フットボール部のチーム「フライヤーズ」に3年籍を置いて、クオーターバックやハーフバックをやった。チームは地区のリーグ戦でも強豪で、何戦何勝したかは覚えていないが、私が在籍中に一度地区優勝した。私は地区リーグで優秀選手に選ばれ、学内では4年生の秋に優秀学生賞を受賞した。これは学業成績や課外活動、スポーツなどいろんな分野でオールラウンドにめざましい活躍をした学生を表彰するもので、これにはフットボールの選手であり、生徒会の副会長をしていたことが大きかったと思う。
高校卒業を半年後に控えた58年秋、ニューヨーク州中でいろんな優秀賞を受賞した高校生を一堂に集めて開催するディナーパーティーがあり、マンハッタンの会場に行った。そこで私の大学進学を大きく左右する、思いがけないことが起きた。それもフットボールでの表彰が縁だった。
ダートマス大
奨学金で縁の名門へ ホ一ケーに興じた寮生活
1958年、高校最後の学年の秋。表彰パーティーの会場で、中年の男性が近寄ってきて「ダートマスでフットボールの選手にならないか」と誘ってきた。私は既にカトリック系の名門、ノートルダム大学に進学する予定で準備していたし、大学でフットボールの選手になるつもりは全くなかった。
そこで断ると、「君の学業成績は」と聞いてくる。私は平均96点だと答えた。実際、学年2番の成績で卒業した。1番の学生は私より平均点が0.2高かった。「それじゃあ、ぜひダートマスヘ行きたまえ」とその男が言った。彼はダートマスのOBで、すぐに大学から入学願書と高額の奨学金申請書類を送ってきた。当時の授業料が年に3千ドルだったのに対し、奨学金が1800ドルもあった(今日では授業料が2万5千ドルくらいだと言うから隔世の感があるが)。
それまでダートマスは名前しか知らなかった。だがここに進学することを決めた。理由は第一に東部アイビーリーグで非常にいい大学だという評判が高かったからで、第二には高額の奨学金が出るので両親の負担が少なくて済むからだった。わが家の家計には実に大きな祝福だった。
高校を翌59年6月に卒業し、9月には17歳で初めてニューハンプシヤー州のダートマス大に向かった。両親が衣類や本をスーツケースや車のトランクに詰め込んで、ニューヨークの自宅から北へ7時聞半運転して現地入りした。モテルに一泊し、翌日、私が入学、入寮の手続きを済ませると、二人はそのまま帰宅した。
両親はダートマス大がアイビーリーグの名門というレッテルにはほとんど頓着せず、ニューイングランドの濃い緑の森と丘陵、川の自然の景観に恵まれた美しい魅力的なキャンパスであることに大喜びしていた。
私は広大なキヤンパスに感動していた。不安も少しあっだ。森の中の男子校だ。正面の一番大きな図書館には地下の閲覧室の壁一面にメキシコの代表的な芸術家、ホセ・クレメンテ・オロズコが30年代に描いたダイナミックで劇的な壁画がある。キャンパス内のフッド美術館には同窓生が寄贈した世界中の歴史的な芸術品が多数収蔵され、展示されている。ハノーバーというのはダートマスのある静かな町で、町の人たちは学生に優しく、学生たちは町で年中、いろんな催し物をしていた。
シャミネード高からダートマスに入った学生がもう1人いて、同じ寮に住むことにした。寮は寝室が4つに居間があり、8人で一緒に住むことになっていた。全員で同じ友愛団体に属し、仲良く過ごした。ニューハンプシャーの冬は非常に寒い。私たちはよく友愛団体の建物の裏の駐車揚一面にホースで水をまき、水浸しにしておいた。翌朝には凍ってアイスホッケーができたからだ。寒くてもビールを飲めば飲むほど、からだがよく動いてホッケーがうまくなったものだ。
一番近い女子大が車で1時間半もかかるところにあって、週末には女の子たちの顔を見に「遠征」と称して出かけた。友人が運転する車に5、6人がギュウ詰めに乗って行った。私は奨学生だったので車がなかった。車が持てるほど裕福だと奨学金が差し止められてしまうのだ。だから同僚たちほどひんぱんには「遠征」しなかった。これは本当だ。
大学司法委員長
学生の不祥事を処分 厳しい経験、決断力を磨く
大学生活は素晴らしかった。毎年、厳寒の2月には大学名物のウインター・カーニバルがあって、キャンパス中に大きな氷の彫刻を作って並べた。ユーモラスに彫るのが条件で、わが友愛団体は海賊バイキングやおどけた小人たちを作った。トナカイやドラゴンも勢ぞろいして壮観だった。近隣地域から見物客がたくさん集まった。
友愛団体対抗でフットボールやホッケーなどいろんな競技もやった。だが私はフットボール部には入らなかった。アイビーリーグには運動部員への奨学金がなかったからだ。新入生の時にはボー卜部に入って、クルーでボートを漕いだ。1年生は毎朝4時に起きて川に行き、5時半から漕ぎ出すのだが、まだ夜明け前で暗く、猛烈に寒かった。だがそれも2年目に練習時間が午後遅くに変更になり、科学の演習時間とぶつかってしまったため、ボートをあきらめざるを得なかった。
いろんなクラブ活動に参加した。ラジオ部員になって、大学で放送しているラジオ番組のコマーシャル時間を売るため、町の店屋を戸別訪問して広告依頼もした。学生自治会の執行委員もやった。
中でも特筆すべきは司法委員会活動だ。学生の不祥事について事情聴取し、相応の処罰を下す機関で、わが人生に重要な影響を与えた思う。
学業に関する不祥事は直接教授会にかけられるが、公序良俗に反するような不祥事、例えば泥酔、女性を寮に入れる(当時、寮内は女人禁制だった)、許可時間を過ぎても騒いでいる、学生同士で乱闘、傷害事件を起こす、窃盗、器物破損などの事例は、学生で構成する司法委員会が処分の判断をすることになっていた。
私は3年生の時に級友に選ばれて司法委員になり、4年生の時に学部長の指名で委員長になった。事件の連絡が学生や学内警察からあると、委員長が調査を委員に命じ、委員が関係学生や警察、教授、目撃者らの話を聞いて報告をまとめる。
委員会はたいてい毎週火曜の夜7時半に開かれ、深夜から午前2時くらいまで続いた。委員の報告をもとに、被告生に出席を求めて言い分を聞く。その学生を退席させて待機を命じ、委員だけでさまざまな角度から検討し、妥当な処分を決める。実際の法廷とよく似たやり方だ。
結論に達すると、委員長として被告の待つ部屋に行き、「規律違反で有罪につき停学(退学)処分」などと宣告しなければならない。処分を聞いて泣き出す学生もいたし、激怒して食ってかかる学生もいた。息子が放校処分になることを心配して、両親が付き添う場合もあった。 これは実に厳しい経験だった。同時に人間的に成長せざるを得ない体験でもあった。何しろまだ20歳か21歳で、他人の一生を左右するほどの決定をしなければならないのだから。私の委員長時代、停学・退学の決定を下したのが8件ほどあった。
ただ、わわれの決定はすべて大学当局の審査を受けることになっていた。決定後一両日中に私が学部長室に行き、教授で構成する委員会と学内警察署長に対して、われわれの決定の妥当性を主張する。そのまま認められるのがほとんどだったが、1件だけ、われわれの処分が軽すぎる、と修正されたことがあった。
大学を卒業
60年代後半、社会激変 工学士、関心はビジネスヘ
司法委員長をやって学んだことの第一は、状況を調べるのに早い段階で結論づけてはならないということだった。事実は必ずしも最初に報告された通りではない。十分に調査し、分析し、しかも可能な限り内在的に理解できるまで判断を留保して、その上で初めて公正な目で結論することの大切さを学んだと思う。
学内警察が学生を連行してきた時には、たいてい学生は重罪犯扱いされるものだ。そこで私たちはしっかり調査し、事実は必ずしも警官の言う通りではない、などと議論していった。女の子が寮に入っていたのが見つかったといっても、わずか5分だったり、雨が降り出したからだったり、何人もの学生と一緒で、おかしなことなど何もなかったから、学生を処分するのはおかしい、などと議論した。ただし、そうした状況でなかったら、寮に女性を連れ込んだ学生は放校処分だった。
委員長として小さなチームを運営するのも非常にいい勉強になった。委員会はたいてい6−8人編成で深夜まで議論する。どうやって全員が審理を尽くしたと合意し、納得できる共通理解に導いていくか。それはチームを引っ張っていく指導力の問題だった。
第三に、私たちがどう結論を出したか、判断の根拠は何かをすべて口頭で要領よく要約することの重要さを学ぶことができた。司法委員長は教授会や警察署長に対して、この事件の学生には特別に寛大な処置で済ませる、あるいは全く処罰する必要がない、ということを論理的に説得しなければならなかったからだ。
63年に卒業し、6年ほどたって同窓会で大学に戻った時のこと。友愛会館の2階に行くと、不意に女性がシャワー室から出てきた。驚いて、あわてて階段を駆け下りながら「一体、私は何をしていたんだ」と自問してしまった。何よりショックだったのは、自分が退学処分にした根拠がその後、規則違反でも何でもなくなっていたことだった。
60年代には急激な社会変化が起こり、それに対応する形で大学の規則も様変わりした。今日では大学の寮はほとんど男女共用になっている。
60年代後半の大学生たちは「フラワー・チルドレン」と呼ばれ、既に私たち旧世代の者とは感覚が非常に違ってきていた。私は別に自分の世代とその後の世代とを比べて、どちらが良くてどちらが悪いなどと価値判断するつもりはない。ただ少なくともダートマスが男子校だった時の方が勉学にいそしむにはよかったと思っている。
その学業の方だが、哲学が大好きで、哲学コースでは優等賞をいくつももらった。ダートマスの成績評価はAからEまでで、ほとんどの学科でAを取ったが、Cがひとつだけあり、それは專攻した工学コースの機械作図だった。私の卒業資格は工学士だった。
入学した時、ダートマスの工学部が優れていることは知っていたし、将来は技術者かビジネスマンになることを考えていた。だが工学コースを勉強するうちに技術者になる気をなくしてしまった。それよりもビジネスの世界に行きたいと思うようになった。
学部を卒業して、ダートマス大のビジネススクールに進学しようかとも思ったが、ここの大学院は当時まだ規模が小さく、院生も目立たなかった。どうせ大学院に行くなら東部でも最も評価の高いハーバードの方がいい、と考え直した。
ビジネス校入学
ハーバードで猛勉強 事例研究、隔週でレポート
1963年秋、首尾よく奨学金付きでハーバード・ビジネススクールに入学できることになり、ボストンに移った。同じニューイングランド地方といっても、ニューハンプシャーの寒い山の中の小さな大学町から暖かい港湾都市のボストンに移るのは、日本で言えば札幌から東京に引っ越すようなものだった。気温も文化も活動も大違いだった。
ハーバードは猛勉強を強いるところだった。特に1年目がきつかった。当時は土曜日も授業があり、週に6日授業に出なければならなかった。授業はすべてケーススタディーだった。具体的な事例を読んで議論する。それまで高校、大学では読書して事実を集め、分析して正解を考えるという古典的な教育を受けてきた。だがこうした事例研究では正解がない。最初はそれに戸惑い、ややイライラした。
最初の授業はよく覚えている。ある会社で経営幹部が大きな失敗をした場面で、教授が「経営トップとしてはどうすべきか」と聞いた。ある学生が手を挙げて「みんなクビにする」と大きな声で言った。教授はその学生に「そうか。では誰が会社を動かしていくのかな」と質問をした。
それは以前とは非常に違う新しい学習方法だった。ハーバードが事例研究に優れていることは聞いていたが、どんなふうに指導するのかは知らなかった。しばらくすると、このやり方がとても気に入って、楽しめるようになった。
ハーバードは作文指導でも優れていた。隔週で事例研究のレポートの提出が義務づけられ、土曜日午後5時までに郵便受けのような箱に投かんしなければならなかった。レポートの枚数は8−10枚。簡潔に、かつ効果的に分析し要約する訓練になった。翌週には成績評価が発表された。
レポートはすべてタイプでカーボンコピーを取っておかなければならない。だが私はタイプが打てなかった。学生ホールの掲示板にはいつも「レポートをタイプします」というアルバイトの紙がたくさんはってある。その大半は大学院生の妻たちで、立派な家内工業として栄えていた。
ところでハーバードが女性を学生に受け入れ始めたのは私が入学した年からで、同級生に女性が2人いた。卒業後、1人は銀行に、もう1人はマンハッタンの超一流店に就職した。今日では多くのビジネススクールで女性が半数近くを占めるようになっているという。
当時のビジネススクールでは、私のように学部を卒業してすぐ入学した学生が多かった。だが今日ではもうそんなことはない。米国の一流ビジネススクールはどこも学部卒業後数年は社会経験を積んだ者でないと入学させなくなったからだ。
私の学年では社会経験4、5年の学生が何人かいた。今でも親しい友人の1人は妻子持ちで、私たち独身伸間はよく彼のアパートを訪ねては、奥さんの手製の料理をごちそうになった。そのお返しで時々、子供たちの世話をした。
ハーバードで会計、財務、生産、組織など有益な基礎知識を学んだが、そうした知識は実はもっと別な方法ではるかに効率よく、しかも金もかけずに習得できるだろう。ここで学ぶ最も重要なことは、状況がはっきりしないまま、限られた情報と限られた時間の中で、いかに事態を分析し、判断を下すかということだ。
マッキンゼーへ
就職、GM研修が契機 コンサル、メーカーに絞る
もう一つ、ハーバード・ビジネススクールで学んだ重要なことはチームで仕事をすることの意味だった。一人で作業することはむしろまれで、たいていの事例研究は集団で議論した。少なくても2、3人、時には6人編成でやった。
チームで学ぶことは、ある人たちはまじめに仕事し、ある人たちはしないという現実だ。宿題もちゃんとやって自分の考えをしっかり述べる人がいれば、黙っていて、ちゃっかり他人のアイデアをちょうだいしようという人がいる。自分の意見を簡潔に付け加える人がいれば、冗舌にひたすらしゃべりまくる人もいる。何も話すべき内容もないのに発言したがる人もいる。 チームメートのそれぞれの性格や気質がよくわかった。社会に出て、仕事上、最も重要だと思うのは人を見る目を養うことだ。人物を見抜いて、やる気を起こさせ、適材適所に配置し、適切な指示を与えることだ。そうした人物評価の基礎訓練を、大学院のチーム作業で学んだと思う。
大会社の経営者ともなれば、自分で何もかもできるわけがない。いくらコンピューターの設計が好き、営業が好き、経理をしたいと言っても、CEO(最高経営責任者)としてはすべて他人に委ねるしかない。チームのメンバーを選び、信頼してまかせ、その仕事ぶりを評価するしかないのだ。
さて今、米国ではMBA(経営学修士号)が有益で価値があるものかどうかについて論争が起きている。私自身はそれに十分説得力のある判断は下せないと考えている。第一にMBAの優れた学校もあれば、たいしたことのない学校もあるからだ。非常に優れた学校が指導者を多数輩出しているのはたしかだが、それはその学校に行ったから指導者に育ったのか、もともとそうした資質のある人たちが学校に行ったのかがわからない。
私にとってハーバードはとても重要な意味を持っている。何しろ入学した時、まだ21歳の若者でしかなかったし、MBAを取得するまでに夏休みの企業研修など、いろいろと仕事する経験を積むことができたからだ。
1年目の夏にはまだどんな分野に就職したいのかもわからず、ゼネラル・モーターズ(GM)の労務部門で研修した。厳しい労使交渉を間近に見て、経営側の責任者が非常に優れていたことに感心し、研修後には「よし、就職するなら経営コンサルタント会社か強力な商品を抱えるメーカーだ」と考えた。当時のハーバードではこの2分野が幅広く学べる職種として最も人気があった。
翌年、私は両職種の会社の面接をたくさん受け、最終的にプロクター&ギャンブル社とマッキンゼー社に絞った。前年の夏、実はマッキンゼー社に研修希望を出したが、断りの手紙をもらっていた。それが今回は採用すると言う。他社からも多数、合格通知が来ていたが、マッキンゼーに決めた。入社は65年の夏、23歳のときだった。
面白いことに、入社1年後にMBA採用担当になって、私が1年の夏に受け取った手紙は「今後ともあなたを採用するつもりは全くないので、二度と就職希望してこないように」という意味のこもった手紙だったことを知った。ごく最近、マッキンゼー社の経営陣と会った時にその話をしたら、大笑いになった。
試練
「他の仕事探したら・・」、指導係の言葉バネに昇進
ニューヨークに本社のある経営コンサルタント会社、マッキンゼーに入ったのは65年6月のことだった。この会社のプロとしての仕事ぶりに感心していたので、就職できてうれしかった。ここでは昔も今も社員が信念を持って建設的に指導力を発揮しようする風土があり、それが質の高い仕事をもたらしていた。
会社は当時、社員が400人ほど。活動地域は北米がほとんどで、欧州ではロンドンと、フランクフルトにオフィスがあった程度だった。その後、1970年代に大前研一氏が日本支社長になったように、営業拠点を広げていった。
私の初任給は8500ドルプラス・ボーナスで年収約1万ドルだったと思う。当時でもコンサルタント会社は最高レベルの給与を出していた。
入社して最初の仕事はモービル石油社の役員報酬問題の研究だった。マッキンゼーは当時、多くの企業の役員報酬問題を扱っていた。私はもちろん報酬問題も石油業界も全く知らない。並んだ顔ぶれの中でも一番下にいるので幸いだったが、社内では猛スピードで駆け上がることが期待されており、数日後には自分より数十歳は年上の企業役員と面談するようになっていた。
新入社員は「ニュー・アソシエート」と呼ばれ、4、5人編成のチームで基礎的な調査をするのが主な仕事だ。先輩や上司の指示に従って資料を読み、事実関係をチェックし、要約し、分析し、図表化する。新人の仕事はどこでもたいして変わらないだろう。
マッキンゼーは特に若者にとって非常に挑戦しがいのある職場だ。ごく普通の問題にも相当な難問にも同じように取り組み、顧客企業の重役と交渉し、基本的な事項についても学べる。常に自分を駆り立てていなければならず、決して気が休まることがない。
入社2年目に、私の指導係だったパートナーと食事した時、丁寧な口調だが「どこか他に仕事を探した方がいいんじゃないか」と言われた。彼がなぜそう言い、それに私がどう応じたのかは覚えていないが、実に厳しくも貴重な体験で、決して忘れられない。彼の言葉はその後もずっと私の中に生きていて、率直かつ正直に話すことが相手のためになること、他人の精神的な支えになることの意昧について考えさせてくれている。
彼の言葉が励みとなり3年後にパートナーに昇進した。それも最年少記録だった。当時は同期入社の7人に1人の割合でしかパートナーになれず、1人がなると他の6人は退社した。それは「アップ・オア・アウト(昇進か退社か)」と呼ばれた。努力なくして成功なし。若い社員には過酷な職場環境ではあった。
そこは同時に、社会人として働くことの意味を学ぶ場でもあった。
入社3年のころ、創業者で専務のマービン・バウワー氏が私の部屋に入って来て「社会へのお返しに何をするつもりかね」と聞いてきた。とっさのことに戸惑いながら「学生時代に借りたローンをできるだけ早く返済するようにしています」と答えた。すると「いや、そんなことじゃなくて、もっと意義のあることだ。今日アメリカの公教育を立て直す活動をしている組織の会合があるから、手伝ってくれないか」と誘われた。専務の言うことを断るわけにはいかない。「いいですよ」と言って一緒に出席し、それから35年たった現在に至るまで、私はずっと、この公立学校再建運動に深くかかわってきた。
転職を決意
経営そのものに興味 アメックス、魅力的な誘い
入社3年後の1968年、26歳の時に結婚した。職場が同じニューヨーク市内にあり、銀行の融資担当をしていた彼女と知り合い、何でも話した。
マッキンゼー社ではきわめて順調に仕事し、出世していった。社内では私は「駆け抜ける男」と評されていた。パートナーになって交際範囲が広がりゴルフを始めた。自分の顧客として全部で30社ほど直接長く担当し、あと30社ほど短期で助言してきた。
そこで学んだ最も重要なことは、担当する会杜の基盤が何かを精細に理解することだった。マッキンゼーは顧客企業の市場性、競争力、戦略の方向性について深く分析することに強くこだわった。コンサルタント業とは深い分析力と意思伝達力と顧客に変革を起こさせるよう仕向ける能力を組み合わせたものだ。優れたコンサルタントは優れた分析をし、その結果を顧客にうまく伝え、それを確実に実行させなければならない。
私には何年も担当してその会社が成功するのに重要な貢献をしたと自負できる大企業が3社あった。そうした会社のトップとは非常に親密になり、見返りも大きかった。
入社9年でシニア・パートナーの地位まで昇進し、財務部門の責任者となり、さらに社業のかじ取りをする上級リーダーシップ委員会のメンバーとなった。金融サービス会社など主要顧客3社の責任者となり、その第1位がアメリカン・エキスプレス社だった。同社はパートナーになる前、入社4年目ごろから担当していた。
マッキンゼーの企業文化は何よりも優れたアイデアを最優先させるというもので、私もそれが大いに気に入っていた。素晴らしい発想、鋭い洞察力がすべてであり、課題の解決に役立つことが言える人、考えをさらに先に進められる人には皆が素直に耳を傾けた。だから往々にして会議で議論をリードするのは、必要な調査を済ませ、考えを練って提案できる若い人たちだった。年次肩書きなど組織上の序列主義はなかった。
だが入社10年が過ぎて30代半ば近くに「このまま20年もコンサルタントは続けたくない」と思うようになった。たしかに知的刺激に満ちた仕事で、素早く行動し、大手企業の重役たちと付き合うことは楽しいが、助言者役を演じ続けることに大きな不満を抱くようになったのだ。
企業トップのところに分析結果と具体的な行動計画を持参して、なだめたりすかしたり言葉巧みに説得し、同意を取りつけたところで、コンサルタントはお役御免となり、事務所に戻る。計画の実行段階ではいないのだ。だが「私はテーブルの向こう側に座ってコンサルタントを雇い、決断し、実行する人間になりたい」と思うようになった。
コンサルタント会社を辞めて別な職業に転身するのは少しも珍しいことではなかった。事実、世界中至る所でマッキンゼーOBが自分で事業を起こしたり、政府の役人や政治家になったりしている。日本支社長だった大前研一氏も東京都知事選に出馬した。
そのころ、私にもたくさん転職の誘いがあった。その大半は私が担当した企業からだったが、いろんな理由をつけてすべて断っていた。どれも退社を決意するほどの魅力がなかったからだ。だが、アメリカン・エキスプレス社からの誘いは非常に魅力的だった。そこで77年、35歳の時、転職を決意した。
アメックス社
旅行関連部門の長にTCとカードを共存共栄
1978年にアメリカン・エキスプレス社に移った時、私はこの会社がきわめてユニークで素晴らしい会社だと信じることができた。コンサルタントとして8年担当して、この会社の幹部はみんなよく知っていて、好きだった。当時はクレジットカード事業の草創期で、この事業には大変な将来性があると思えた。
普通、コンサルタントが実業界に入ると、戦略部門や企画部門のトップに就くことが多いが、私は業務部門を担当したかった。だから旅行関連サービス(TRS)部門のトップの職に就いて喜んだ。ここはアメックス・カードと旅行小切手(トラベラーズチェック=TC)の発行、旅行代理店業務を担当し、従業員も数万人いる主要部門だった。
新しいポストの報酬がいくらだったか覚えていない。たぶんマッキンゼー社で得ていた年収とほとんど変わらなかったと思う。転職を決めたのは報酬額が魅力的だったからではなく、アメックス社の膨大な組織の長として実際の経営ができるという点にひかれてのことだったからだ。
当時のアメックス社は、その120年の歴史の中でも最大の課題に直面していた。同社が普及させたTCは、大成功の主力商品として続いている。そこにクレジットカードが登場したが、売り上げはまだわずかだった。だが多数の金融サービス機関がTC事業に参入する一方、数百行もの銀行がほぼ一斉にビザ、マスターカードを使ってクレジットカード発行事業に乗り出し、アメックス・カードと競合し始めていた。そうした中でTRSの担当者たちの多くは「クレジットカードを持てば、TCは要らなくなるのではないか」と心配していた。カードがTCへの脅威となり、この2商品は対立するものだと考えていた。
そこで私の第一の仕事はTCの良さを保持しながら、同持にカード事業を発展させていくことだった。競争が厳しくなっても、市場をグローバルに考え、新商品とサービスを幅広く提供することでTRS部門はダイナミックに成長する可能性があると考えた。
アメックス社の11年間は非常に楽しく、満足できるものだった。TRSの収益は10年間に毎年17%の伸びを示し、純益は78年から87年までに500%増を記録した。カード発行枚数は800万枚から3100万枚近くまで伸び、海外での発行にも力を入れ、取り扱う外国通貨の数は11から29に増やした。コーポレート・カードを中心に全く新しいビジネスを生み出し、通信販売やカード処理部門でも新しいビジネスを展開した。88年には通販部門だけでも全米第5位の大手に成長した。カ一ドを紛失しても24時間以内に再発行するサービスも導入し、高品質文化を築いていった。
昨年末、ハーバード・ビジネススクールのジョン・コッター教授が「大企業における起業家精神」の成功例として私のアメックス時代の業績を取り上げた論文を書いている。実際はそれほど簡単かつスムーズに達成できたわけではない。そうなるまでいろんな障害や抵抗があり、文字通りの文化革命が長く続いた。
最初の数ヶ月は、よく直属の部下たちが反乱めいたことを起こした。実情を調べるのに、組織の階層に関係なく一番詳しい者から直接話を聞こうとすると、飛び越された中間幹部たちが「困る」と騒いでいたのだ。
大企業を変える
起業家精神植え付け IT戦略の重要性を認識
アメリカン・エキスブレス社に移って、大企業ではどの組織も誰かに任せなければならず、序列に従って業務を遂行するのが当然であることがよく理解できた。指揮命令系統をできるだけ配慮し、尊重するように努めた。
だが重要な問題に取り組む場合には、何より優れた知恵と知識を注ぎ込むことが大切だと考え、よく現場に近い管理職の人たちを呼んで会議を開いた。現場の人間こそ私の知りたい事実や情報を持っているからで、一緒にテーブルを囲んでざっくばらんに議論した。彼らの上司が出席しても、私はもっぱら部下たちとばかり話した。時には上司を呼びもしなかった。
議論する時には意図的に素っ気なく、しかも威嚇するような物言いでどんどん厳しい質問を浴びせるようにしていた。社員たちが会社の弱点、矛盾点を克服するための戦略を探るように仕向けるためだ。問題解決のためにもっともっと自由かったつに議論しようというメツセージを社内に浸透させるねらいだった。
同時に、上司たちに対しては、事実を掌握して問題に真剣に取り組み、解決策を打ち出して行動するのが本当の管理職であり、単に手続きにこだわって段取りをこなすだけの監督官ではダメだというメッセージを送り続けた。私は、組織の中で決められた手順を守り、会議ばかり開き、承認の署名をするのが自分の仕事だと考えている管理職をずっと軽べつしてきた。彼らは社業に実質的に貢献する人たちに反対し、邪魔をするからだ。
そこで全社的に起業家精神の文化を育てるため、不要な官僚主義的な手続きを省くことを励行する一方、知的なリスクを負う努力をする社員を奨励し、表彰する制度を導入した。人事管理が苦手で日常的な業務処理がうまくできない者でも、優れた考えを持ち、いい提案ができる者なら厚遇する人事制度をつくった。
さらに組織再編と人事異動をたびたび行った。それは幹部たちに社外にどんな有望な機会や脅威があるのかに強い関心を持ってもらい、社内組織の硬直化を防ぎ、社内政治にうつつを抜かすことをやめさせたかったからだ。だから管理職をひんぱんに部署間で異動させて派閥グループを壊し、部署間の激しい縄張り争いを減らした。旅行関連サービス(TRS)部門のトップとして社員に「あなたはカード部の人間でも、小切手部の人間でも、旅行代理業務部の人間でもない。TRSの人間なのだ」と強調し続けた。
私はのちにTRSの業務命題を8つの原則にまとめた。業界で最高の商品を提供すること、品質の高いサービスこそが最も競争力の高い武器になること、常に顧客のそばにいること、社員の価値を高めることーーなどで、14カ国語に翻訳して世界中のTRS社員4万4千人に配った。
私がIT(情報技術)の戦略的な価値を考えるようになったのもこのころだ。アメックス・カードを見れば、それが巨大な「eビジネス」(そんな言葉は1970年代には存在しなかったが)であることがわかる。何百万もの人が毎日、世界中を旅して数十カ国で支払いにクレジットカードを使う。その請求書が毎月、自分の通貨で換算されて手元に届く。それがすべて世界中の膨大なデータ処理センターで電子的に処理されているのだから。